眼の神殿
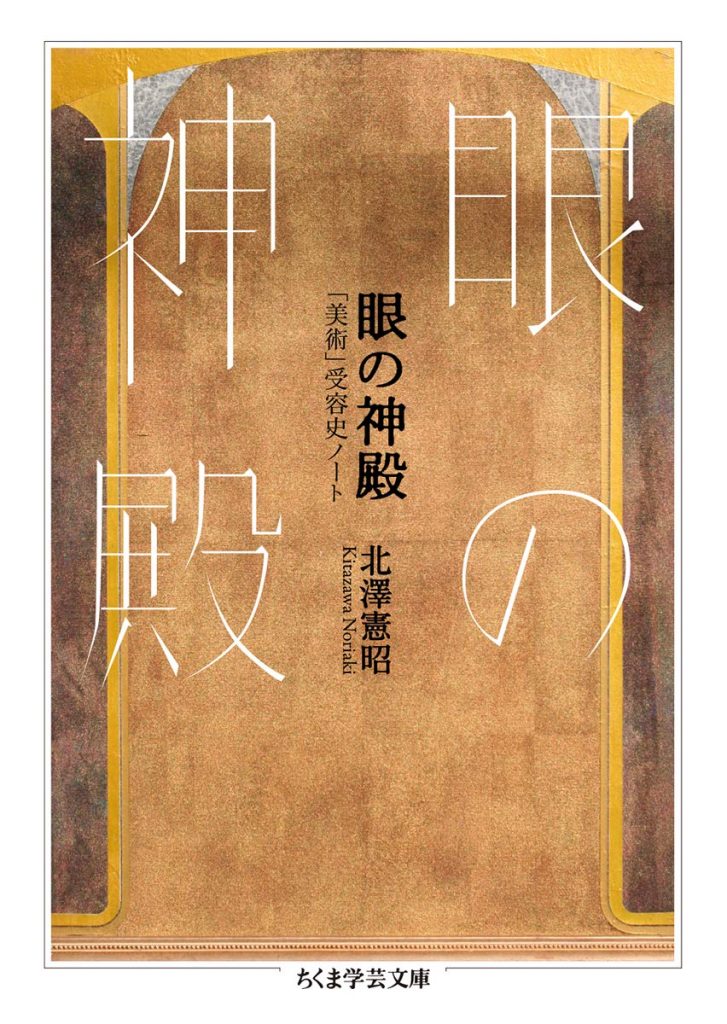
美術史研究を一変させたと言われる本書を何となく手に取り、ダラダラと読んだ。著者の引き締まった文体を差し引いても継続して読むのが難しい本であった。問題は、僕の側にこの分野の知識と興味が無く、面白さを見つけるための手掛かりが得られなかったことだ。普通こういう本は紹介しないのだが、『読んでいない本について堂々と語る方法』に倣って少しだけ書いてみる。
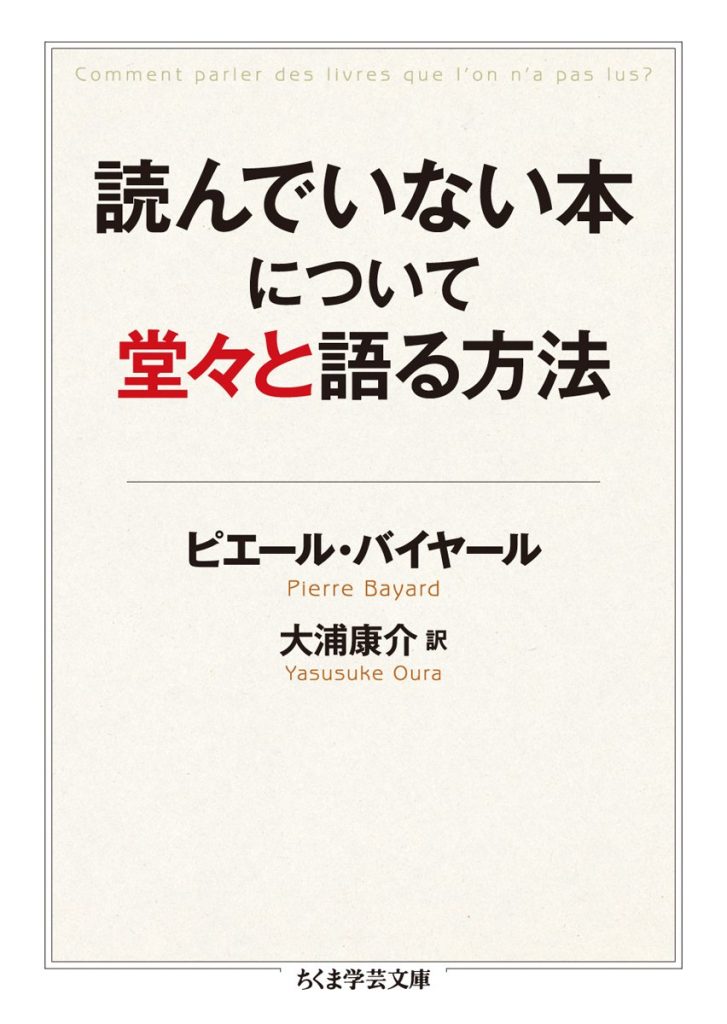
本書によると、「美術」という言葉は明治の初めに西洋から移植された概念であり、”schöne Kunst” (fine art) が原型にある。書画、工芸、芸事一般を指し示す概念である「芸術」ならそれ以前から存在した。そこから「視覚で捉える造形芸術」を抜き出したのが「美術」であるのだが、この枠組みに定着する迄には近代以降の諸制度の構築を待つ必要が有った。そして近代以前も含めた「日本美術史」もまた制度の歴史という側面を抜きに語ることができないことを本書は示した。つまり、制度的視点からの美術史。ここに本書の革新性があるらしい。
以上は非常に大雑把な要約である。恐らく間違いがあるかもしれない。思うに本について何か語るということは、深い容器の底に入っている物体を上から覗いてその形を判別するようなものだ。少しずつ水を注ぎ、撹拌するとその物質が水面に浮かび上がって来ては又沈む。水の量が不十分だと光が届かず、撹拌量が足りないと一面しか見えない。本書に沈む核はそれ程複雑なものではない。ただ水量(読解度)と撹拌量(興味、自身が持つ他知識との関連)が少々足りなかった。

