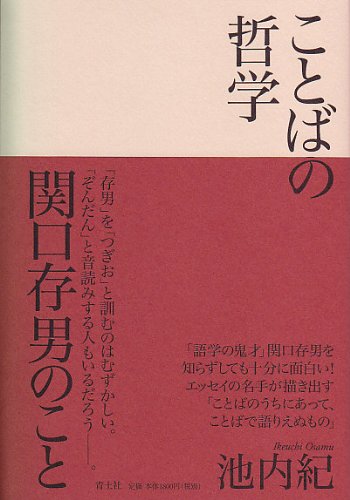語りえぬものを語る
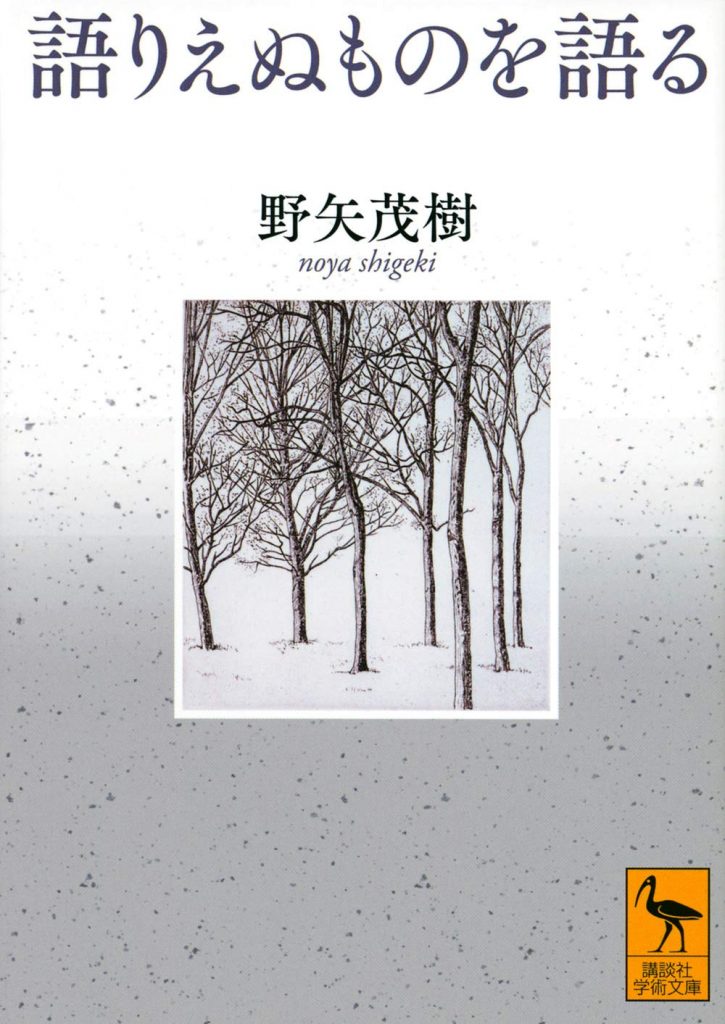
年末から年始にかけて、通勤電車内や、休みの日は喫茶店などで毎日少しずつ読んだ本である。この本は本当に面白かった。この類の本はその内容が読者の知識レベルを少しだけ上回っていると楽しく読める。苦行にならない程度の軽く負荷のかかった運動、例えるなら緩やかな坂道を自転車で上るに似た充実感が得られる。僕と同程度の教養がある人なら、多分世の中年の大半が当て嵌まると思うが、内容に興味さえ有れば同様に楽しめると思う。
本書は全26章、一章ごとに順を追って著者の哲学の(本書が書かれた時点での)到達地点へと考察を進める。出発点となるのはウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の終着点、「語りえぬものについては,沈黙せねばならない」である。そして第一章「猫は後悔するか」。ここで少し解説を挟むと、ウィトゲンシュタインにおいて「語りうるもの」とは論理空間の内部を指す。「論理空間」とは現実に起こった事実と現実には起こらなかったが起こりえた、又は将来において起こりえる可能性の全てを含む。ここで言う可能性とは論理的に矛盾しないという非常に広い意味での可能性である。どんな突飛な空想であれ、言葉で思考しうる限りそれはその人の論理空間に含まれる。現実の世界はそんな論理空間のごく一部に過ぎない。
一方で僕たちは現実の世界に生きている。現実に知覚し、経験し、分節化した事柄を核に論理空間は形成され、そして刻々と成長する。(ということは、経験を積めば積むほど、子供より大人の方が、より大きな論理空間を持つ。論理的には歳を取ればとる程より自由な思考ができるとも言える。)ここで重要なのは分節化という言葉である。現実の世界そのものは分節化などされてはいない。だからこそ科学は世界を説明しつくせないと著者は語る。「そもそも世界は語りつくせないのである。」「実在は、自然科学を含め、言語によって語り出されるあらゆる理念的世界からずれていく。」少々話が先走った。科学に関しては最終章(第26章)で語られる。
然るに論理空間は、言い換えれば可能性の空間は分節化された言葉を核に形成される。さもなければ、言語において様々な組み合わせを試すことができないからである。つまり可能性とは、分節化された言語を用いた表現としてのみ成り立つ。それゆえ、分節化された言語を持たない動物は可能性の空間を拓くことはできない。かくして、「猫は後悔しない」。ただ現実に相対するのみである。以上は第一章の非常に大雑把なつまみ食いであった。
論理哲学に関して知識は無いが上に書いたような話題に興味を惹かれる、という人にこそ本書はお薦めである。翻訳に関することや僕たちが知覚する世界の相貌に関してなど、本当に沢山のことに思いを巡らしたのだが、それらはもう僕の記憶から滑り落ちてしまった。2020年中に読んだ前半部分は僕が2020年に読んだ本の中で最も面白いものの一つであり、そして今年に入って読んだ後半は現時点(1/7)で文句なく2021年のベストである。
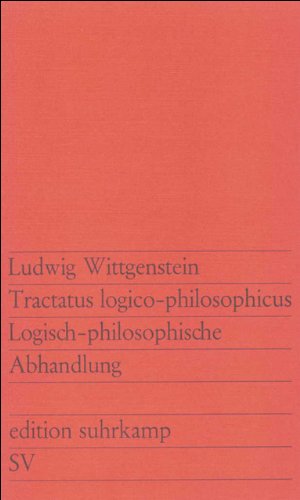
以下余談になるが、『論理哲学論考』の原著はドイツ語を勉強した折に読み通したことが有る。辞書を引きつつ何とか一通り目を通しただけで、内容は何も理解できていない。これだからドイツ語が一向に身につかない。『論考』を選んだ理由も薄いからであった。僕と同郷の天才語学者、関口存男はドイツ語の習得に取り掛かった際に、当時手に入るドイツ語で書かれた本の中で最も分厚いものを一冊購入し(『罪と罰』のドイツ語訳であったらしい)、単語の意味も文法も全く何も知らないまま、暇さえあれば本を手に、暗唱できるまで繰り返し読んだそうだ。そうして暗唱を繰り返していると、一年以上たったある時期を境に突如として自分が口ずさむドイツ語が意味を成して理解できることに気付いたという。悪夢として見そうな話しではある。