ことばは国家を超える
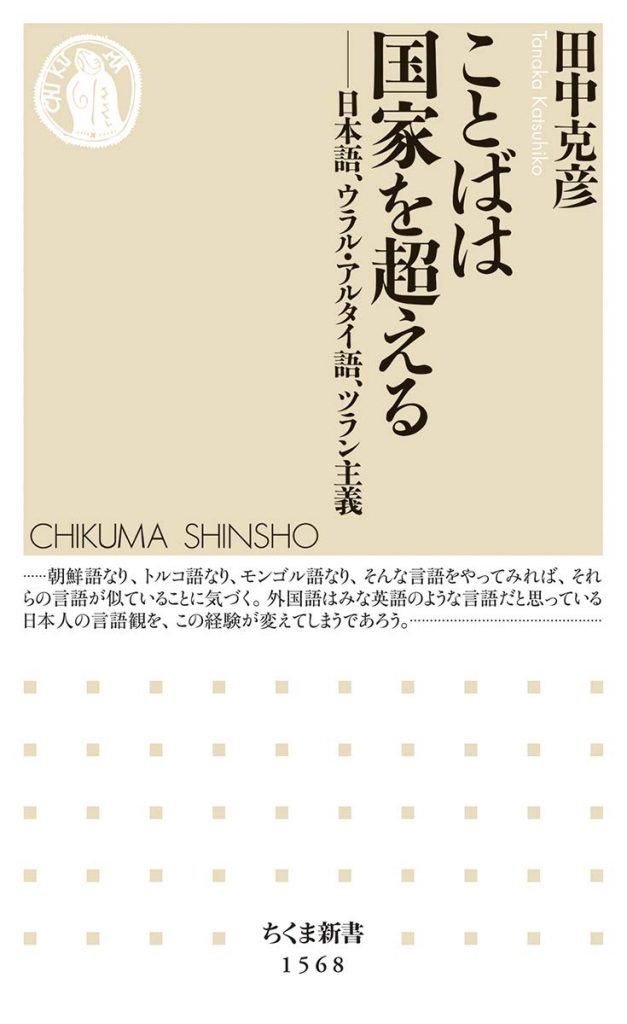
この系統の本は久しぶりである。著者は他にも『ことばとは何か 言語学という冒険』、『言語学者が語る漢字文明論』、『漢字が日本語をほろぼす』などを出版していて、僕はもうそれらの内容を忘れてしまったのだが、特に最後のものについては一理(か多理)は有るとは思いつつ、随分と極端な主張をするものだと少し距離を置きたくなった気分のみを記憶している。そんな著者の新刊書をなぜ読むのかといえば、趣味で語学学習を愛好する者として、この類の本を読むのは義務的に感じるからである。読まないと、気になって仕方が無くなるのだ。そして読めば、必ず面白いと感じるものが見つかる。
さて本書であるが、端的に言えばウラル・アルタイ語族を中核にした比較言語学の本である。この語族は元来ユーラシア大陸に広く分布していたのだが、ロシア語と中国語による浸食を受けて使用地域が制限されつつあるのが現状の様である。この語族にはフィンランド語、ハンガリー語、モンゴル語、ツングース語群、満州語群ほか、朝鮮語と日本語が所属する。ユーラシア北東部は言語多様性のホットスポットの一つである。余談になるが、朝鮮語・韓国語の表記にはいつも迷う。「韓国語」が最も馴染みがあるのだが、そう表現すれば北朝鮮と中国北東部の朝鮮族を無視することになる。NHKはその辺りに配慮して「ハングル講座」としている。日本語での正式呼称が何なのかは知らないが、本書では「朝鮮語」としていた。歴史を背景にした用語、或いは「朝鮮半島周辺の言語」という意図だと思う。
本書の第一章において、ユーラシアに分布する言語の幾つかは、所謂インド・ヨーロピアン語族とはどこか異なり、これらを一括してウラル・アルタイ語族というファミリーに纏めることができそうだぞ、という認識と受容の歴史が描かれる。この語族に属する言語に共通の特徴として膠着語であるということの他に、母音調和する、Rから始まる言葉が無い、などが挙げられる。「母音調和」とは、一つの単語内で使用できる母音の組み合わせが制限される現象である。例えばフィンランド語では “y, ä, ö” と “u, a, o” は同居できないので、何らかの理由で混成が生じる場合(語幹に人称語尾が付くときなど)、どちらかの音が許容される音に置き換わる。日本語の音の変化にもこのルールが働いているのかもしれない。Rから始まる言葉が無い、というのは日本語を思い返せば「なるほど」、と納得がいく。少なくとも僕が知る限りで、ラ行から始まる大和言葉は無い。それらしいものが有ったとしても、語源を調べれば中国語由来だったりする。フィンランド語辞書でもRの項目は少ない。
第二章では言語を分類する方法として音韻則と類型論が説明される。音韻則的には音の変化が積み重なって新しい言語が生じる。ここから「祖語」という概念が生まれるのだが、音韻変化を遡上して復元される祖語は「ミトコンドリア・イブ」と同じく学問上の概念に過ぎない点は注意しておく必要がある。音韻や単語の変化は周囲の言語環境と密接に関連するので、音韻要素を言語の「遺伝子」として抽出し、其れのみを変化要素として復元することにどれだけ意味が有るのか僕には分からない。
類型論では言語構造の全体像に注目する。つまり「文法」による分類である。以前読んだ本から、文法は無意識的な言語運用ルール(スキーマ)を意識化・規則化したものであり、それ故より直感的で根本的な分類、ということになる。屈折語・膠着語・孤立語などのことである。この部分は僕たちのスキーマに深く根差しており、語彙を差し替える程度では揺るがない。日本人にとって英語のハードルが高いのもこの部分で異なるからだ。勿論この部分も時間と共に変化し(一般的には単純化し)、例えば屈折語に分類される英語には「屈折」要素がほとんど残っていない。この構造による分類に最初に注目したのがフンボルトであったそうだ。そう言われて思い出したのが以前に聴いた”The Invention of Nature” (audible版) で、シベリア探検の個所にそんなことが書いてあった(言っていた)。
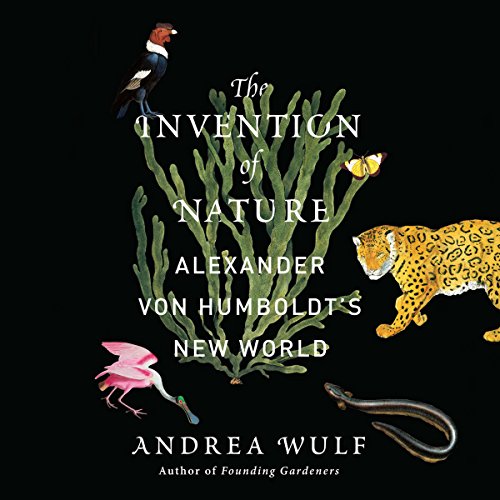
これ以降の内容に触れるのは無駄に長くなるので控える。興味が無い人には無用の知識だろうし、興味がある人は本書のタイトルや目次を捲れば読みたくなると思う。本書について二点だけ苦言を呈すれば、一点目は著者の「文法」の捉え方が限定的であること。孤立語に分類される中国語は単語を連ねるだけなので(それ故「孤立」語という)、文法が乏しいと著者は言う。ここから著者の考える「文法」がどういうものかが分かる。それは文中で語彙の役割を明らかにする要素やその変化規則、そして語順規則のことであると思われる。中国語は僕もその辺りは単純に感じるのだが、語彙の選択と語彙数がその単純さを補っていると思う。それもスキーマの一部、つまり僕にとっては文法要素ということになるのだが、「文法」という言葉の解釈については専門家である著者の方が正しいのかもしれない。
二点目として、全体を通して論述に纏まりがなく、論旨が散らかっている様に感じた。勿論僕の知識と読解力が乏しい所為でもある。が、著者の愚痴がここかしこに挟まれるのが大きな理由である。年齢的にも研究活動を締めくくる時期に近づいた学者として、日本人の言語学研究に対する姿勢や同僚に対する不満点にどうしても言及しておきたかったのだろう。悪意を感じない、公平な視点からの愚痴なので(多分)、特に身構える必要なはい。また、真に受ける必要もない。

