熱力学の基礎
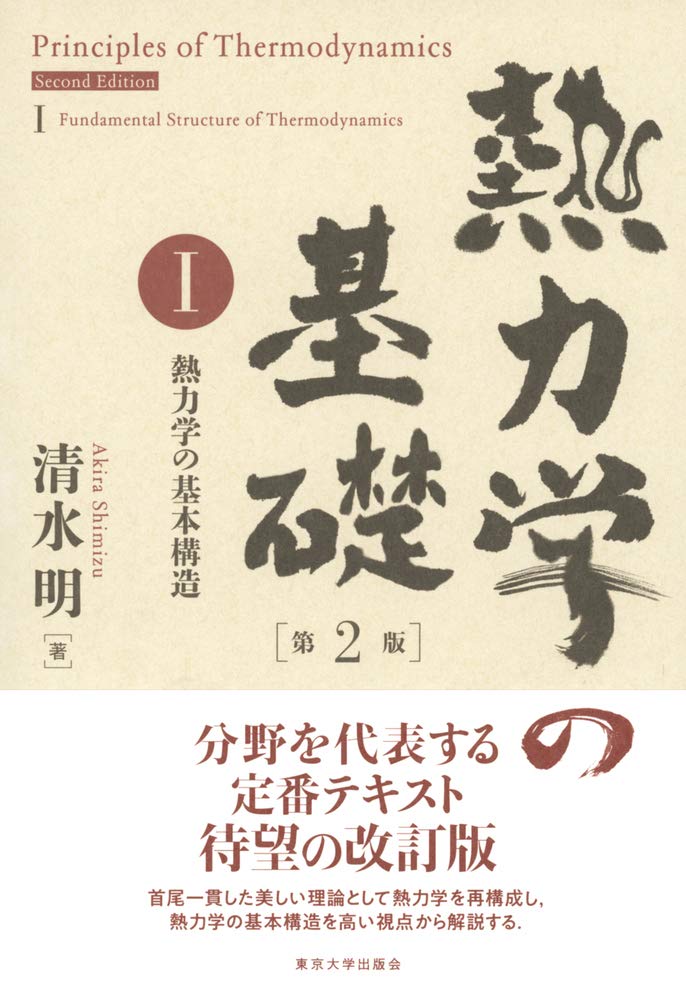
本書は大学の勉強の教科書なので一般の興味は惹かないかもしれないが、当サイトで紹介してきた語学書と同様に僕はこれを趣味の本として読んだので、ここで少々紹介したい。そうしたくなる位に良い本であった。最近喫茶店に通っていると以前に書いた。そこで読んでいたのが本書である。1日1章ずつで全14章、最終章は未だなのでコーヒー13杯分の満足は十二分に得られたと思う。
熱力学は大学教養部の必修講義以来である。その内容は、正直に言えば僕はよく理解できなかった。基本の公式と、どのケースにどの考え方を使うかを覚えれば問題は解けるのだが、根本の部分がどうもスッキリしなかった。恐らく、講師の先生もよく分かっていなかったのだろうと思われる。その分野の専門家でもない講師が義務的に担当することも多い教養部の講義は(当時は)当たりハズレのブレが大きく、どうやら結構なハズレを引いたようであった。物理学などは基本的に必修単位としてしか必要としない生物学科生の一見さんが相手なのでしょうがないのかも知れない。名著と名高いCallenの “Thermodynamics” を取り寄せはしたものの、到着を待つ間に “Molecular Biology of the Cell” を読み始めたので結局そちらは読まず終いになった。
以下、本書の内容を簡単に纏める。あまり詳細に拘ると当サイトを見てくれる人の興味から外れること間違いないので、もし気になる人がいれば本書をあたって頂きたい。用語の定義も省く。もしこの世界の変数を漏れなく抽出し尽くすことができれば、この世界の出来事の全て(物質も出来事に含めて)は数式で正しく書き表すことが可能になる。もちろん、その為の文法も知っている必要はある。この文法を探求するのがミクロなスケールの物理学である。ここを出発点としてマクロな世界、僕たちが知覚し関係するスケール、に言及するのが統計物理学と言える。
一方、本質的に複雑な運動の相互作用から構成されるこの世界の無数に存在する変数から、僕たちのスケールにおいて本質的な統計量たった2,3個のみを取り出し、「平衡」と呼ばれる状態で成り立つ関係を記述するのが熱力学である。この理論はミクロの物理学とは異なり、本質的にスッキリとして強固である。どうしてスッキリ強固になるのかは分からないが、その強固さは現代の物理学の進歩には影響されない。
熱力学の説明には二つの流儀があり、A. 相加変数(エネルギーや体積など)だけを基本的な変数に選んで理論を展開する方式、B. 変数の一部を示強変数(温度や圧力など)に置き換える方式、があるらしい。僕が教養部で学んだ本をはじめ、化学や工学分野で応用を重視する教科書の多くは流儀Bを採用する。変数が経験として分かりやすく、実験でもコントロールしやすい量だからだろう。問題点は、示強変数は相互に影響し合うので、あまりスッキリしない説明になる。先に挙げた “Callen” と本書は流儀Aを採用する。こちらは実用には一手間要る(?)のだが大変スッキリしている。
本書では数学の公理とも言える基本的な要請から理論が構築される。その要請とは、例えば「孤立系を十分長い間放置すれば、マクロに見て時間変化しない状態へと移行し、この状態を「平衡状態」という」などである。エントロピーの存在も要請として前提される。詳細を一つだけコメントしておくと、エントロピーは平衡状態(準平衡状態)においてのみ定義される量であり、それ故に熱力学の理論は平衡状態に制限される。この量はとても興味深く、ミクロな視点において時間上で方向性のない運動(の相互作用)をマクロな視点から眺めた途端、方向性が生まれると言っているのだ。何故そうなるのかは分からない。
エントロピーはエネルギー・体積・物質量の関数である。逆に言うと、エネルギーはエントロピー・体積・物質量の関数でもある。この関数が平衡状態を変えるとどう変化するかが熱力学の全て(多分)である。この理論は現実の系にある量の変化に上限と下限を与え、どういう変化が起こり得ないのかを説明してくれる。さて、エネルギーの関数にある種の変換(ルジャンドル変換)を施すと、HelmholtzエネルギーやGibbsエネルギー、エンタルピーなどの昔聞いたことのある、一般的な教科書では前面に出てくる量が得られる。これらの量は温度や圧力など示強変数の関数なのだが、示強変数は単独で操作できない場合があったり、相転移で注意が必要になるので、なんだかスッキリしなかったと言う訳だ。
目次を見ると下巻ではより複雑な状況下での熱力学が取り扱われる。出版が何時になるか分からないが、その時に興味と時間があれば読んでみたい。

