哲学ってどんなこと?―とっても短い哲学入門
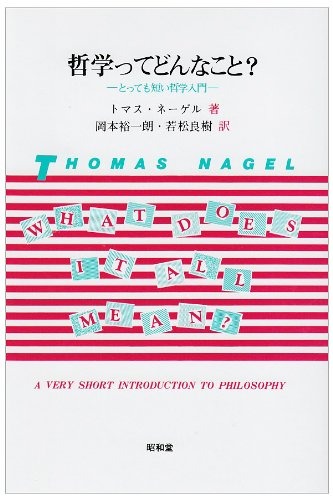
最近、哲学学っぽい本を読むことが増えた。歴史・哲学・古典(文学)の三点セットは歳を取ってくると誰もが一度は興味を持つと聞く。僕は哲学のことをほとんど知らず、一流の哲学者が書いた本格的な哲学書などは読んでも理解できるとは思えない。思想史の中での位置づけも皆目見当がつかないので、先ずは入門的なものを読んでみた。一つ断っておくと、ここに紹介する三冊は数多くある哲学入門書の中で特にお薦めという理由で選んだのではない。僕が読んだというだけの選択であり、未だ読んでいない多数の同類書とは比較できない。
何かの分野に手を出す際、最初に要点を簡潔に総覧できる本を読むのが良い。知識は楽して得るに限る。途中で嫌になって止める可能性が減るし、その知識をどう活用するかの方が重要なのである。僕が大学生の時のT先生はそう教えてくれた(言葉通りではないし、脚色があるかもしれない)。彼は講義の前に度々本を紹介してくれ、それが楽しみでもあった。その多くはもう忘れてしまったが、セリグマンの『オプティミストはなぜ成功するか』や『Essential Cell Biology』はそうやって知った本である。後者は特に彼の哲学を体現しており、当時読んでいた分子生物学の定番参考書『Molecular Biology of the Cell』の情報の洪水に丁度飽きて来たところだったので、 大学レベルには十分な(研究分野によっては不十分だと思う.生態学志向の僕にはそれでも十分過ぎた)知識を押さえつつ一回り丁寧な解説に感心した。最新版は日本語訳も出ていて、(分子)生物学を一通り知りたい人にはお薦めである。
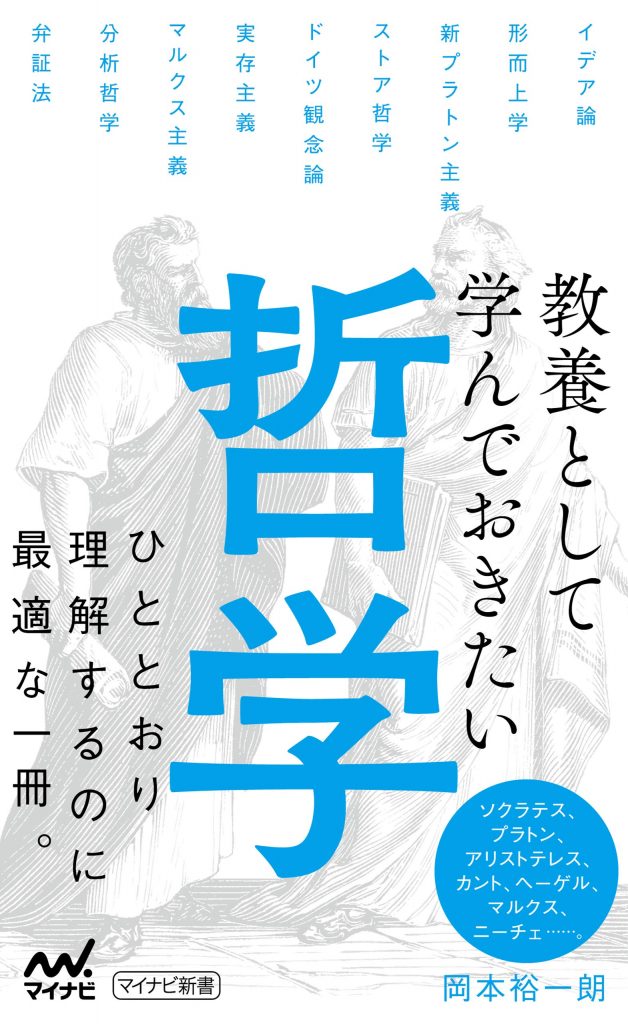
『教養として学んでおきたい哲学』も哲学分野を一望するのに良い本であった。気楽にスラスラ読める本である。哲学にどういう歴史があり、何を問題としていて、誰がどういう事を考えたかが実に簡潔に纏めてある。古代以前において、哲学は万物一般を追究する学問であった。学問は哲学であったと言っても良いと思う。そこから実用面や技術に特化した分野:医学、神学、法律などが抜ける。近代以降は科学や人文学の諸分野も独立し、さて哲学には何が残されているかと問えば、クッキーを型抜きした生地の如く諸分野を抜き残った畦地を縫い動く活動である。より重要な活動がもう一つあって、クッキーの例を用いると生地を広げる土台部分への問いである。土台とは、各諸分野が前提として置いている、そこを疑えば何も成立しえない、その部分のことである。カントは「人間とは何か」と問いを発した。細かく言えば、カントの三区分「私は何を知りうるのか」、「私は何をなすべきなのか」、「私は何を望んでも良いのか」に分けられる。それぞれ、哲学の下位カテゴリー:存在論・認識論、倫理学、宗教論・幸福論に相当する。これは本書の内容のほんの一部分に過ぎない(歪曲があるかも)。僕はKindle Unlimitedで読んだが、紙の本も出ていると思う。

『古代哲学史』は古代ギリシャ時代の哲学の流れを解説した本で、著者晩年の短い著作を纏めて編集したもののようである。僕はこの薄い本の約半分を占める、ヘラクレイトスが書いた文章の断片の翻訳を目当てに購入したのだが、前半の古代哲学史の部分が割と面白かった。重要なこととして、本書も含み一般的に哲学史で紹介される様々な考え方、例えば「万物の根源は水である」など、は当時のギリシャ文化圏人に住む一般的な人々の思考を反映してはいない。それらの思考は進化的に突然変異を伴って表れた一連の思考法であり、都市国家という特異な環境がその発展の土壌となった。生物の進化(変化)に例えると、島状に分布する生物群の各群の間に十分な隔絶と適度な流出入、さらに島群外部からの適度な流入があり、尚且つ繫栄するための資源が十分にある環境では、多様な、そして競争力もある種が分化し得る。古代以前の地中海世界は正にそのような環境であった。タレスやパルモニデス等は都市国家という独立し、奴隷制に基づく自由が得られる環境の中から誕生した。
彼らの説は高校世界史の教科書などではそれぞれが独立した思考の様に見え、それらが一連の大きな流れの中で登場したことを見落としがちである。タレスに始まった根源物質の追及はパルモニデス(「あるものはある、ないものはない」と言った.何だかバカの様に聞こえるが、詳細は本書を読んで頂きたい)を経て変革を余儀なくされ、四元物質へと至る。アトム論も同様にそこに至る流れが有り、それらは孤立して語るべきものではないのである。本書も古典期限定の入門書で、『教養として 』よりはだいぶ骨がある。両書ともに読書案内が有って有難いのだが、本書に挙がる紹介図書はこの分野の学生や専門的に学ぶ人のためのものなので、一般人には恐らく縁がない。
最期になったが、表題書『哲学ってどんなこと?』は『教養として 』に紹介された本の一冊で、ここで取り上げた三冊の中で最もお勧めしたい本である。本書には哲学者の名前や何々論といった知識は一切出てこない。ただ問いの立て方、考え方を示すのみである。高校生・大学生を対象として書かれた本だと思うが、これが結構高度で、舐めてかかると途中で分からなくなる。あとがきによると、著者ネーゲルは現代哲学の論争まで目を配っており、読者は知らず知らずのうちに、現代哲学の最前線に立つことができるそうである。著者には他に『どこでもないところからの眺め』、『コウモリであるとはどのようなことか』など面白そうなタイトルが並び、気になっていた人であった。
これが本当の最後。哲学するということは哲学書を読むことではない。問いを立て、それに考えをめぐらせる行為である。その問いは数世紀前に既に議論しつくされたことかもしれない。適切に問いを立て、適切に考えるための準備は必要である。哲学書を読む意味は其処にある。その辺は、一般的な学問活動も同じ。哲学者の考えや著作を解釈・評価したり位置付ける仕事は哲学学と言うべきかもしれない。なお、T先生には悪いが、僕は性分的に、俯瞰を手っ取り早く得るのは作業感が付き纏うので好きではない。

