哲学入門
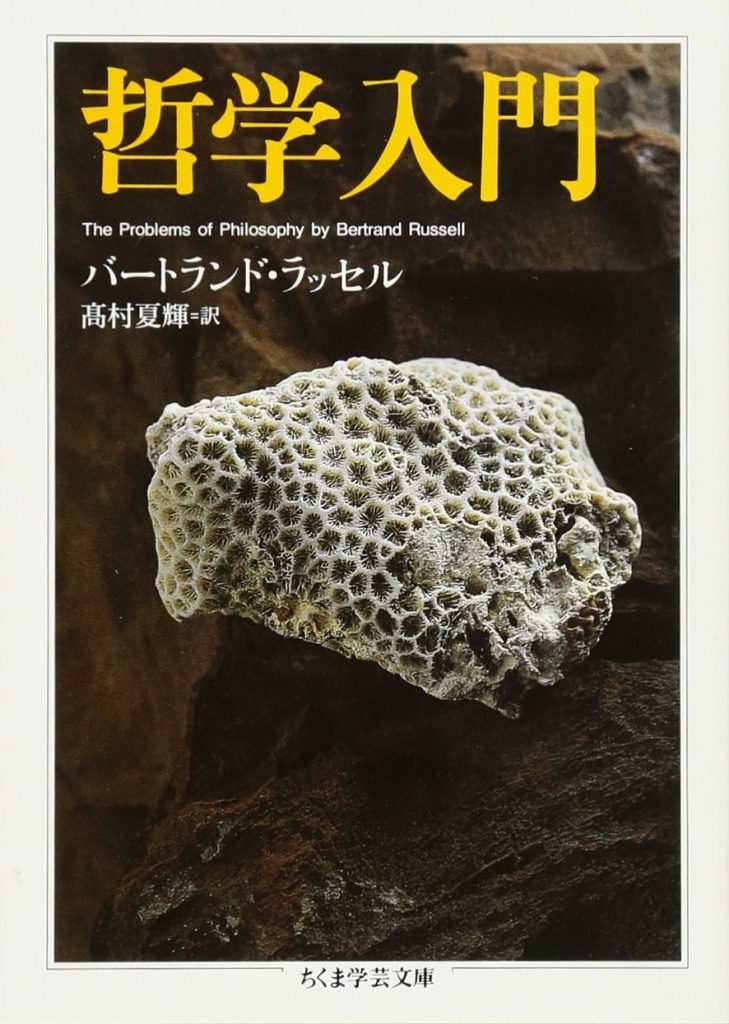
分析哲学の始祖の一人、バートランド・ラッセルが哲学の初学者向けに書いた本である。分析哲学とは、余り理解していないが、言語表現の範囲内で、命題を要素要素に分解し、論理構造を明晰化することを目的とする哲学分野と読んだ。科学的知見や思考実験を取り入れるのも特徴である。本書も哲学全般の一般的な入門書というよりは、分析哲学の入門書というべき内容であった。日常生活で確実なものとして受け入れている多くのものは、吟味してみれば明らかな矛盾に満ちていることが分かる、と著者は本書の冒頭で語る。確実に「確か」と言える、本当に信じても良いものを考察していくと、その次の問題が明らかになる。それは例えばこうだ。
五感が直接教えることは、知覚者から独立な対象についての真理ではなく、センスデータ(五感の知覚)についての真理に過ぎない。そしてセンスデータは知覚者と対象との関係に依存する。したがって知覚者が感じているのはただの「現象」であり、それを知覚者はその背後にある何らかの「実在」の記号だと信じている。では、そもそもその「実在」の有無を知る手立てはあるのだろうか。即ち、物質なるものはあるのか。或いはどういう意味に於いて在るのか。こうして、一段一段と確かな土台を積み重ねていく。その過程は数学と類似しており、その明瞭さが英米で好まれる理由かもしれない。数学と同様に、コツコツと基礎を積み重ねることで誰もがある程度の高みまで上ることができる。
気に入った記述が二つほどある。一つ目は「哲学は、望まれているほど多くの問いに答えられないとしても、問いを立てる力は持っている。問いを立てることで、世界に対する興味を掻き立て、日々の生活のごくありふれたものの直ぐ裏側に、不思議と脅威が潜んでいることをしめすのである」。二つ目は部分部分を繋ぎ合わせた僕なりの解釈に過ぎないのだが、それは次のようなものである。哲学者の著作や発言は彼の置かれた時代背景や社会的立場を前提にしている。プラトンやアリストテレスが何を言ったにせよ、それらは古代ギリシャという環境に置いてのみ「真」であり、時代や立場が変われば恐らくそうは言わなかっただろうと思われるのである。つまり、哲学者の思想を現代に於いて正しく理解するためには、それらを現代版にアップデートしなければならない。マット・リドレーの赤の女王仮説が連想される。因みに、リドレーはまた何か新刊書を出しているのに先日気が付いた。進化学関連ではなかったと思う。
最期に、本書は以前にもAudible版で聴いていた。全体を通しての理解はしていないものの、部分的に数回聴いたのはその英語が非常に明瞭であったからだ。断片断片はとても聴きやすい。これは日本語訳版でも同様で、どの一文、一段落をランダムに選んだとしても、その内容は比較的容易に理解できるように思える。ただしそこで使われる一見何でもない用語には注意が必要で、それらは先行する章に於いて限定された特定の意味や用法を持つようにキッチリと定義されている。その点を見落とすと、議論の流れが良く分からなくなる。タイトルには入門とあるが、それほど気楽に読める本ではない。

