極北に駆ける
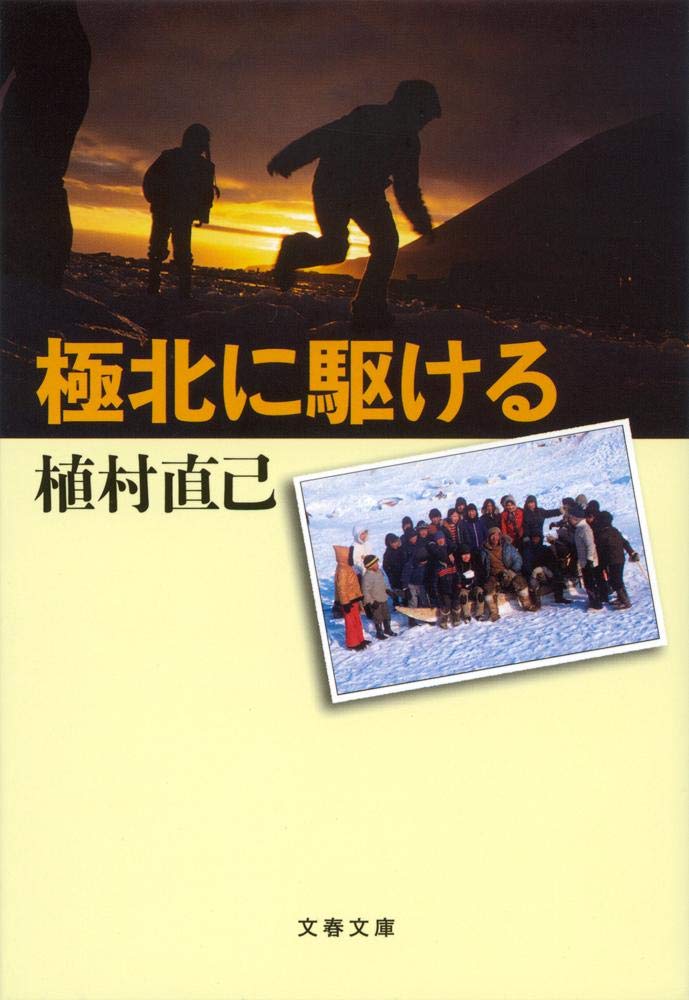
植村直己の著書は『青春を山に駆けて』を入れて文春文庫から計5冊出ていたと記憶しているのだが、先日書店で探してみると現行は3冊のみになっていた。他の一冊、犬橇で1万2千キロ走破するやつ、は山渓文庫に移っており、最も印象が薄い残りの一冊はどうやら絶版になっているようだった。売れなければそうなるのは自然な流れではあるが、少し悲しいものである。
表題書は以降続く犬橇三部作(と勝手に呼ぶ)の第一部で、僕は植村直己の中で一番面白いと思っている。本書はグリーンランド北部に在る世界最北端の集落(当時?)へ、ポンポン船(焼玉船)に乗って彼が向かうところから始まる。これを読むまで僕はすっかり忘れていたのだが、その集落名シオラパルクは実に懐かしく馴染みの有る響きである。続いて「イッキャンナット」「ママット」「アゲショ」など、何度も口にした言葉が次々と出て来た。恥ずかしい話だが、中学生の頃の一時期、僕は本書に出てくるイヌイット語をしょっちゅう使っていたのだ。
植村は偉いと感心するのは、彼が全身全霊を以ってイヌイットの生活に飛び込み、彼らに同化しようと努める点である。同様の滞在記を書いている本田勝一とこの点が大きく異なる。本田勝一の滞在は植村より先行しており、彼はハドソン湾を挟んでシオラパルクの対岸、カナダの集落(名前は忘れた)を選んだ。彼らの生活の実態を当時の日本人に伝えるというライターの立場から、数週間の滞在を通して彼の姿勢はお客さん(理想を言えば定点カメラ)に過ぎず、日本の生活とあまりに異なるイヌイットの生活スタイルに馴染むことができずに不満も出ていた。その顛末を書いた『カナダ・エスキモー』も面白いのでお勧め。
植村がイヌイットに同化しようとしたのは、彼の最終目的である南極点へ、犬橇を使って単独で走破する計画の為であった。その犬橇を使いこなすには、それを日常的な足として活用するイヌイットになりきる必要が有ると考えたらしい。そうして彼は何のつても無いシオラパルクに一人乗り込み、ラジオ体操をして村人の警戒を解き、老夫婦の養子(当時30歳であったそうだが)となる。彼らと同様に鯨やアザラシを狩に出掛け、同様に生肉を食べ、同様に薄暗い家の中で空き缶に排泄する。彼は自身の性格を「臆病」と評したが、こういうこと(他の彼の思い切った行動も含めて)ができる人間を普通「臆病」とは言わない。
以下は少し悲しく情けない話。シオラパルク辺りでは現在はもう犬橇を使った旅ができなくなったという。温暖化により氷が解けて地表がむき出しになったのが原因だそうだ。もう一つ理由として、動物愛護団体の圧力も大きいのだろうと思われる。ペットとして世界中で愛される犬が鞭打たれて酷使されるのが許せない人たちが少なからず居るらしい。頭の悪い人達である。この類の話は本田勝一の頃から出ており、先述の彼の著書(キンドル版のみ?)にも追記のコメントとして載せられている。

最期にもう一つ別の話。昨年フィンランド語に嵌った際に読んだ本の一冊で『サーミ人についての話』があった。昔のサーミ人の生活様式や分化について紹介した本である。原著が書かれたのは100年ほど前で少し古い。因みにサーミ語はフィンランド語と異なるようで似ている(似ているようで異なる?)らしい。サーミ人とはロシア北西部及びスカンジナビア北部に居住する先住民族で、彼らが歴史に登場するのはローマ時代、タキトゥスの『ゲルマニア』まで遡る。トナカイと共に生きる彼らに土地の所有という概念は存在しなかった。その彼らが南から生活圏を伸ばしてくる農耕民(スウェーデン人など)に北のより不毛な土地へと追いやられる様が書いてあり、少し悲しい話である。アイヌともイヌイットとも重なる彼らについて書かれた本書を紹介したいと思いながら忘れていたので、この機会に。サーミ人への偏見と困難が描かれた『サーミの血』という映画もある。

