アーロン収容所
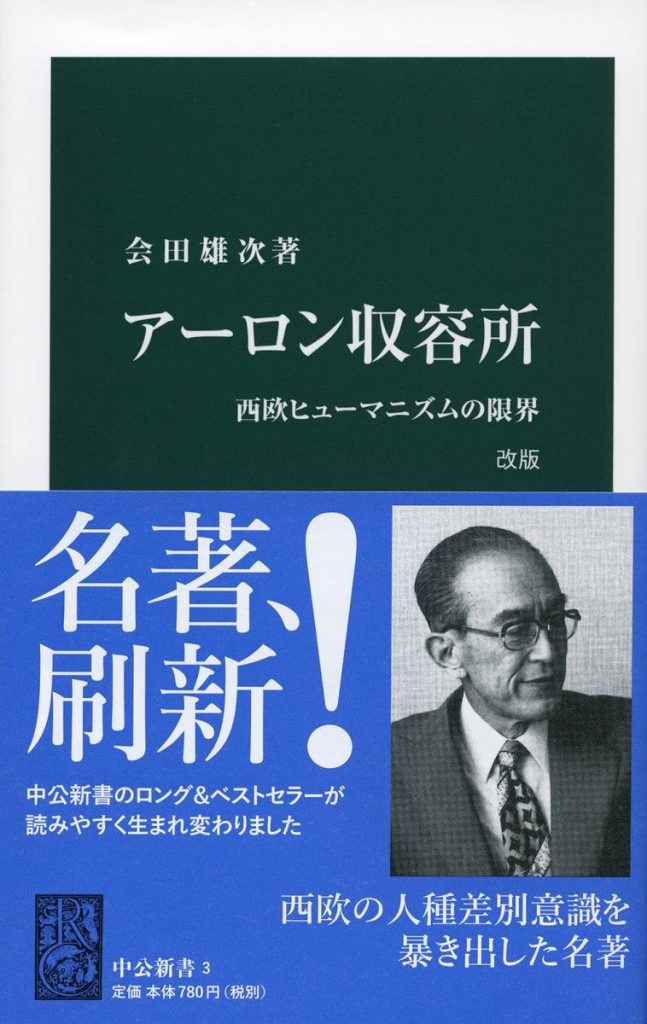
中公新書のホームページだったかうろ覚えだけれど、著名人たちがそれぞれ好きな中公新書三冊を紹介したものを少し前に読んだ。多岐にわたるジャンルの本が取り上げられる中で、きちんとカウントしたわけでは無いけれど、他の本と比べて登場頻度が頭抜けて高いと感じたタイトルが幾つか有った。投稿記事中で最も人気なのは多分『批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義』で、『時間と自己』がそれに次ぐ頻度だったと思う。気になって後日書店で見てみると、両方とも結構硬そうな内容の本だった。紹介者各人の選択には其々のバックグラウンドが強く反映されており、編集者がインタビューしたいと思う対象がそういう分野・背景を持つ人になる傾向が有るだけなのかも知れないが、それにしてもこう何度も名前が挙がるということはそれだけの名著なのだろう。硬いと言っても新書なので、僕もそのうち読んでみたい。
こういう類の企画は大好きで、さて僕自身は何を選ぶだろうかと少し考えてみた。タイトルの一覧が手元にあるわけでは無いので記憶に残っていたり最近読んだものに偏るし、そもそもどう感じるかは読書時の気分や集中度に影響されるけれど、『発酵』、『古代メソポタミア全史』、『トルコのもう一つの顔』、『西洋音楽史』、『外国語を学ぶための 言語学の考え方』、『物語 アラビアの歴史』、『ルワンダ中央銀行総裁日記』は面白かったと覚えている。でも三冊だけ挙げるとするならば、一位から順に『科挙』、『無意識の構造』、『ラテン語の世界』かな。再読すればまた印象が異なるかも知れないが、これ迄に読んだ中では他とこの三冊とでは差が少し開く。岩波新書や講談社現代新書でも、読んだタイトルを思い出すのが大変だけど、同様の三冊を何かの折に選んでみたい。
そのサイトの中で何度か名前が挙がっていた内の一冊が『アーロン収容所』。早速読んでみたところ、お勧めされる理由が良く分かる面白さであった。著者は第二次世界大戦末期に徴兵されミャンマーの最前線に送り出されるが、程なくして終戦を迎えたので実戦の経験はほとんど無く(あるいは実戦の描写が殆ど無い)、部隊全体が英国軍の捕虜としてミャンマーのラングーン・アーロン収容所で数年間を過ごした。この時のご自身の経験に基づいて書かれたエッセーが本書である。日本人達が収容所でイギリス兵から受けた人種差別を著者は後々まで許すことが出来なかったそうで、帰国後に大学の教壇で何度もその体験を口にしたものと思われ、なお収まらずに「とうとう書いてしまった」。
イギリス人の人種差別とはどの様なものであったか。彼らは捕虜の有色人種に対して肉体的な虐待を直接的に加えることは基本的にしなかったらしい。ただの「家畜」として取り扱った。だから著者が室内清掃のために女性隊員の部屋に入室した際、その部屋の住人が素っ裸で居ても、彼女は捕虜ではあるが男性でもある著者の目をまるで気に留めなかったそうである。互いの住む「世界」がヒトとイヌほど違うという認識が骨の髄に染み込んでいるということである。著者を始め多くの捕虜にはこの種類の、残虐ではないが冷酷な仕打ちは応えたらしい。イギリス人など世界から居なくなれば良いとまで言っている。これはこの当時までのイギリスが(多分ヨーロッパ全体が)社会構造として持っていた冷酷さであった。近代ヨーロッパの奴隷貿易などはこの冷酷さ無しには成立し得ない。
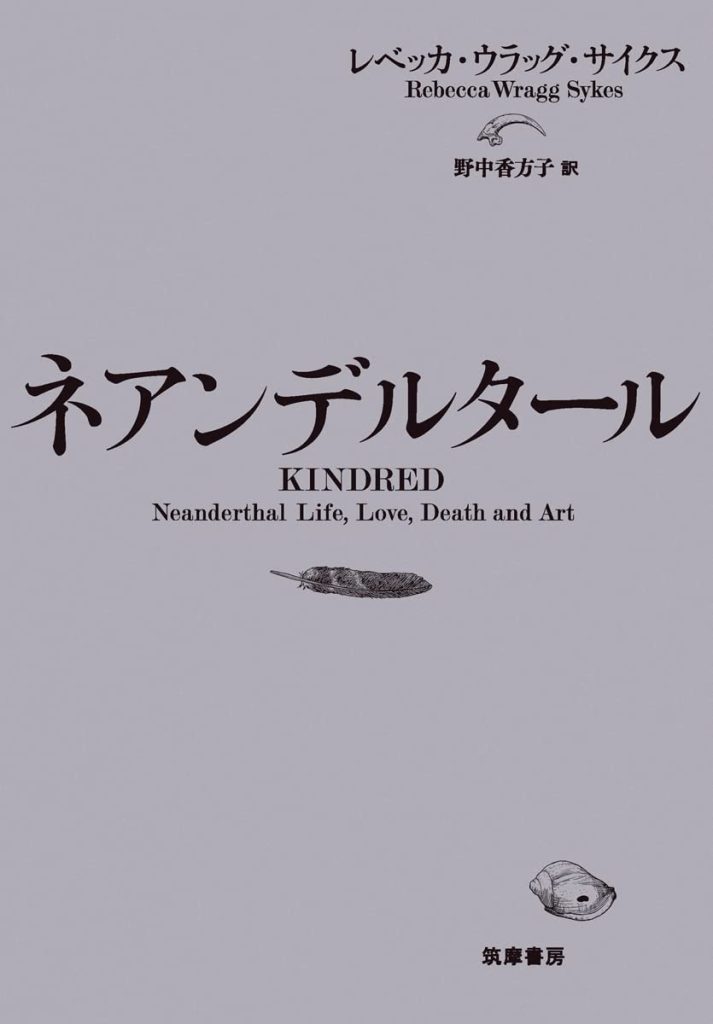
この項は元々こちら『ネアンデルタール』を紹介しようと思って書き始めたのだけれど、そのついでにと書き足すつもりだった中公新書のホームページ記事と表題書だけで少し長くなってしまったので、本書についてはまた後日に。ネアンデルタール人についてこれまでに分かった事実や仮説を一般読者向けに総覧した本である。

