ネアンデルタール
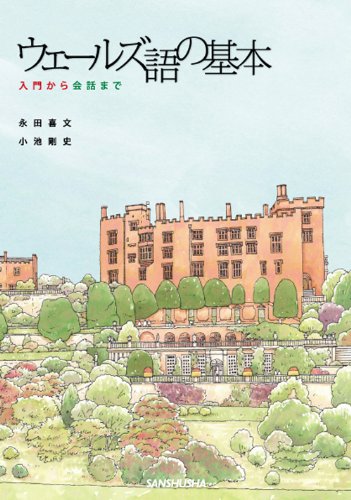
最近またフィンランド語(のテキスト)にはまっている。僕が一押しの『フィンランド語トレーニングブック』は小出しにされる文法事項とその練習問題が見開き1ページに載る構成で、人によっては味気なく感じるかもしれないが、軽いクイズを解いている様で癖になる。フィンランド語に対する親近感は発音が殆どローマ字読みで済むのと、「てにをは」的な膠着要素が日本語に似ているからかもしれない。両言語は厳密にはそれぞれ別の語族に分類されているようだが、僕にはハトコ程度の親しみが感じられる。昔、同じ高校に同級生のハトコが居ると母から聞いたことが有ったが、それが誰なのかは分からず仕舞いだった。そんな距離感である。その例えを続けると、英・独・ロマンス語は友人でラテン語は友人のお母さんってところだろう。同時に読んでいる『フィンランド語文法ハンドブック』の方は所々しんどい箇所もあり、特に初学者がサラッと流し読むと、後半で解説される受動態過去や分詞、不定詞辺りから色んなものがこんがらかって来ると思われる。僕が今そんな状態である。
目的も無く言語の学習に時間を費やしては忘れるという趣味に嵌っているのは、その行為がコンピューターRPG的だからかもしれない。コツコツと経験値(知識)を増やして行動範囲を広げる点と、恐らく何の役にも立たないだろうという点で多分共通していて、RPGに嵌りがちな人には語学(特にマイナー言語)はお勧めなのである。RPGと言えば、僕が唯一時々遊んでいるのがWarcraft。11月末に導入される新拡張に向けた大型パッチが入ったと聞きいて早速再開し、大きく変わったインターフェイスや複雑化したタレントツリーを弄っていると、それだけで何だかお腹一杯になってしまった。語学の方にも何時か飽きが来るのだろうか。
等と思いつつ、『ハンドブック』の方がもう読み終わりそうなので今週から新たに読み始めたのが『ウェールズ語の基礎』。初めてのケルト語である。ウェールズ語とフィンランド語は『指輪物語』を介して繋がりがあり、後者を再開した時から始めたくてウズウズしていた。本書をチラッと捲って見るとアルファベットの綴りと読み仮名(下にカタカナで振ってある)が一致しておらず発音が難しそうに感じるが、これは単に “u” を 「イ」と読んだり “y” を「ア」か「イ」と読むなど、僕たちが慣れているローマ字読みから少しズレるのが原因なだけで、慣れれば難しくはない。
でも発音はやはり難しく、歯で舌を挟む “th”「ス」や “dd”「ズ」、”ll”(エル・エル) に対応するサ行に近い音(舌先を上前歯の裏に着け、舌の側面から息を出して出す音)が頻出して、日本人にはかなり辛い。文法面でも、第一章で出てくる「私は~する」のような簡単な表現が、ウェールズ語になると「私は~(例えばパンを食べること)の中にいる」的な言い回しになり、更に印欧語族なので当然人称変化が付いて回ってややこしいことこの上ない。古風ともいえる。親近感はせいぜい昔の友人の知人並み(つまり知らない人)である。ただ、数字には素人目にも印欧語魂(共通のDNA)を感じた。

もう一冊、最近パラパラと眺めていたのが上の本。教養主義とは何だろうと調べてみると、wikiでは大きく分けて6種類の解釈が紹介されていて、例えば「古典を尊び、学問する生き方を大切にすること(B1)」や「学問などを通して人格形成に努力すること(B2)」などと定義されていた。そこで書いてある内容からすると僕自身も教養主義的な人間に違いなく、それもA2(一々定義は書かないけれど)とB1が合わさる「リベラル・アーツ主義」という分類枠に属するらしい。分類は何であれ、この教養主義と「余談」は親和性が高い。
高校時代に世界史への興味から読んだ『項羽と劉邦』は別にして、30歳の手前まで日本人の小説は殆ど読んで来なかったのだが、とある切っ掛けから読み始めた彼の長編で一気にその虜となった。小説を書き始める度に近所の古本屋で買い込んだと言われる関連書籍から得た知識や見解をチラ見せした「余談」に惹かれたのである。各章頭に物語の舞台背景の解説を挟む小説は有名どころだと『レ・ミゼラブル』等が思いつくが、特に必要という訳ではない無駄知識を物語のど真ん中に堂々と挟むような小説は、彼以前には僕は(そもそも余り知らないので)知らない。余談ではあるが、彼よりは後年、『ジュラシック・パーク』のマイケル・クライトンも英語圏でそういう書き方をした(或いはメジャーにした)代表的作家かもしれない。
余談が入ると物語の流れが中断されるので好きではない、という層が有ることは十分理解できるが、余談は彼の本が出版された時代に流行した教養主義と上手く嚙み合った、という話であった。その他にも様々な要因が彼を後押ししたのだが、詳細は本書を読んでいただきたい。僕はちゃんと読んでいないので詳しくは書けない。彼の著作では『菜の花の沖』『播磨灘物語』など数編の長編小説のほか、紀行文(朝日文庫で出ているやつ)がほぼ丸々未読で、そのうち読みたいと思う。
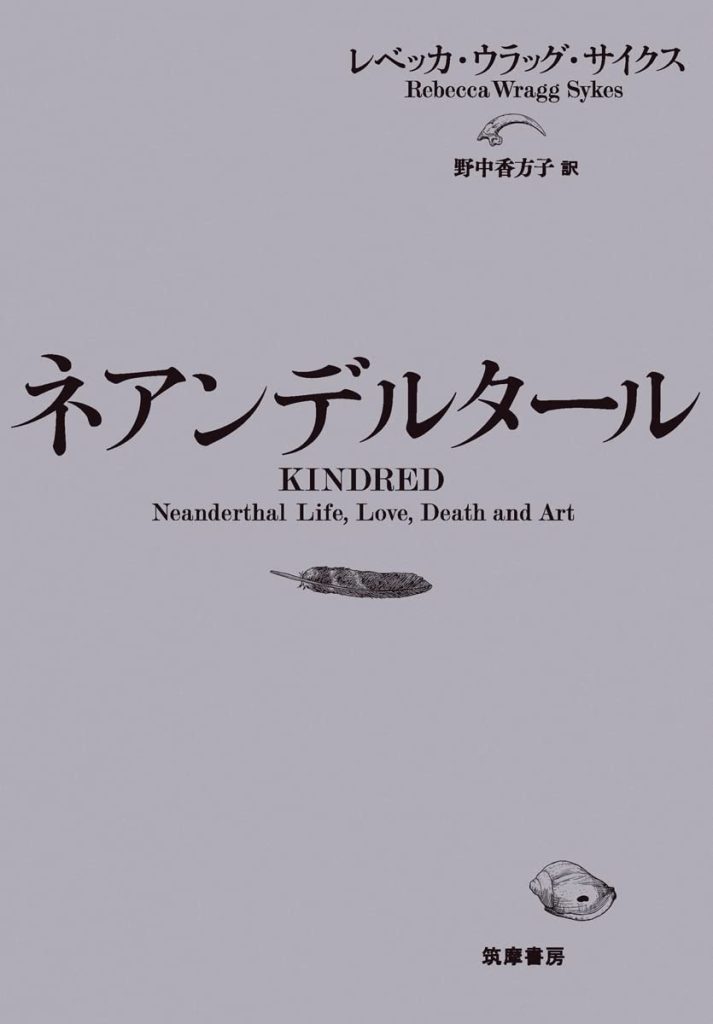
そして表題の『ネアンデルタール』。遺伝解析については少し前の本にも書いてあったように、アジア人には約5%、ヨーロッパ人にはその半分くらいの割合でネアンデルタール人の「血」が入っているらしい。ネアンデルターレンシスとドイツ地名由来の名前が与えられてはいるが、熱帯から亜寒帯までユーラシアに広く分布した、遠い血縁という訳である。この統計はたった40個体の骨のDNA解析の結果であり、未解析の個体はまだ100以上(数百?)有るそうな。さて、何か言いたかったことが有ったのだけれど、一週間以上放っておいたら何処かに行ってしまった。本書は多分、今現在で手に入る一般読者向け(つまり非専門家向け)のネアンデルターレンシス本としては最も詳細かつ多岐にわたる内容なので、興味があれば読んでみると良いかもしれない。ただし、石器、装飾品などの遺物や骨の分析などは素人が興味を保って読み続けるにはかなり詳細で、幾らか根気が要る。それでは、Da bo chi (ダ ボ ヒ)。

