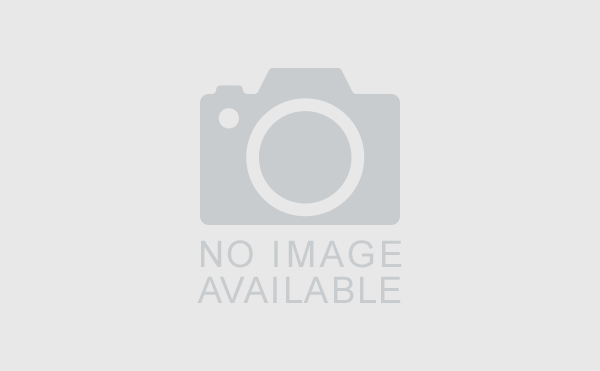未来をつくる言葉 他
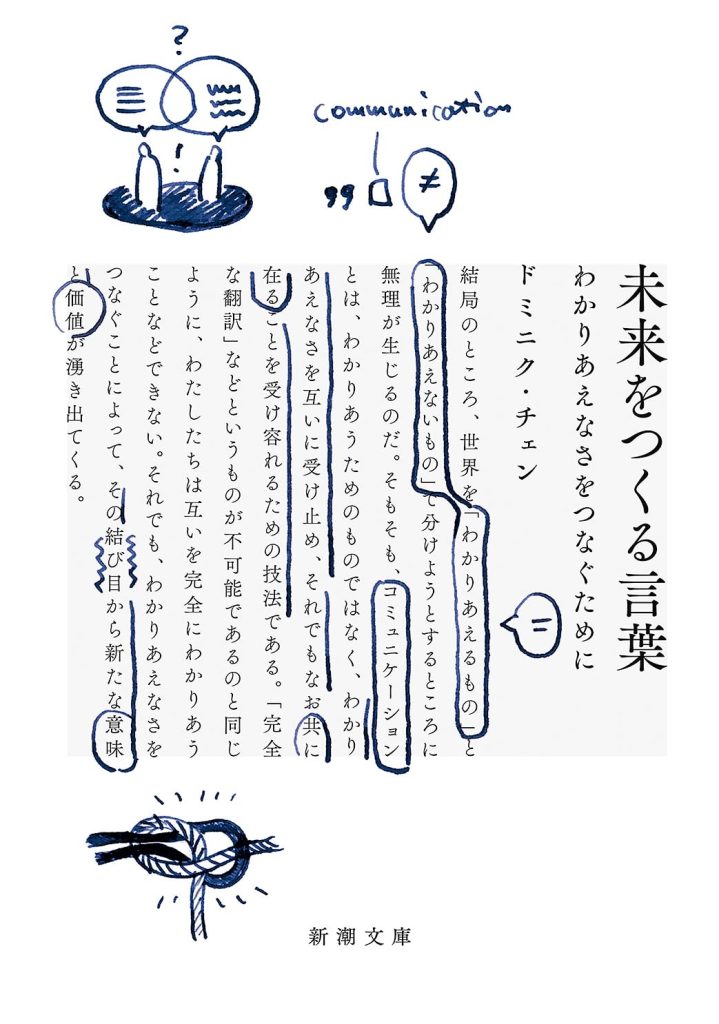
なかなか面白く読んだ本の印象などを手短に。先ずは表題の『未来をつくる言葉』。日本語とフランス語を母語とする著者が、言葉と世界について思索したことを、娘の成長を軸にして綴ったエッセイである。世代が近いこともあって共通体験(?)が多々あり、そのため上から教授を受ける(内容を丸々受け入れる)のではなく、僕ならどう考えるだろうかと折に付けて本を置き思索を巡らすような読み方になった。ただ中盤から後半部分にかけては興味を引かれなかったので飛ばし読みで済ませる。「共話」という言葉を知ることができたのが一番の収穫である。
以下は読書会用のメモ
「正反合」と「守破離」、著者の様には考えない
母語的バイリンガルとモノリンガル、僕にとって英語は日本語の幹に接ぎ木された言語、それゆえ差異より共通性の方が気になる
サピア・ウォーフ仮説 単語が無いのは必要ないから、輸入・説明で補えるならその言語の範囲内
言語の起源は一つ?それとも? 「あなたの人生の物語」(メッセージ)のヘプタポッドの言語、文字の起源は複数?
共話について
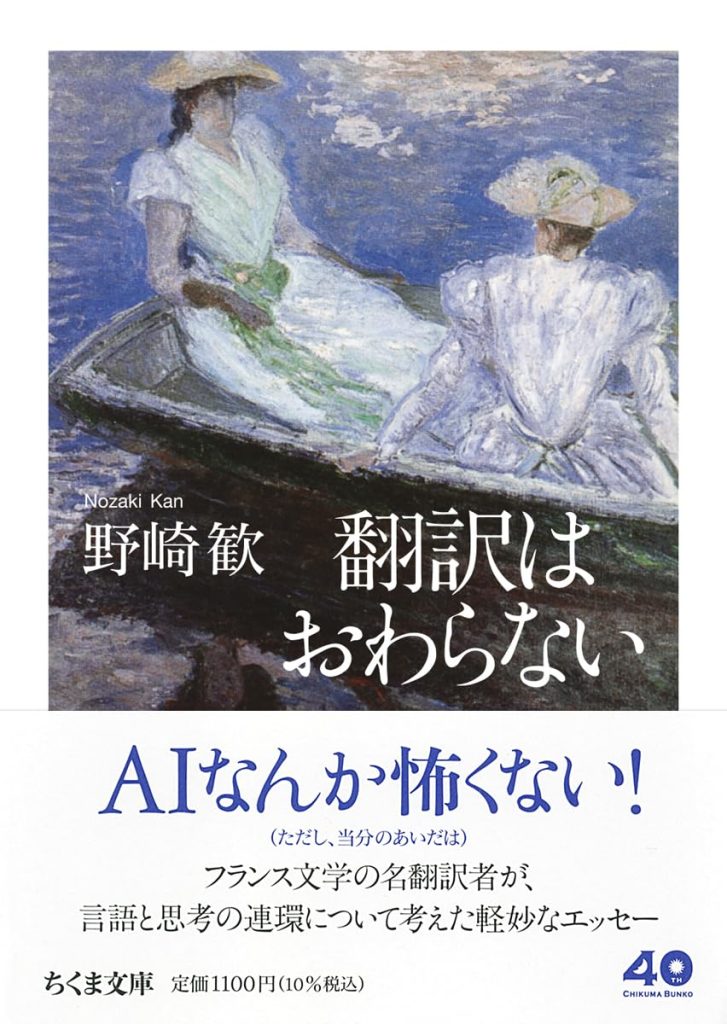
『翻訳はおわらない』は仏文学の翻訳者が翻訳に纏わるアレコレを綴ったエッセイ。上の本と違って物思いにふけるような内容ではなく、只々話の流れに任せて読み進めることができ、いい意味で入眠効果が得られる。クラシック音楽の部分と森鴎外に関する箇所が面白い。
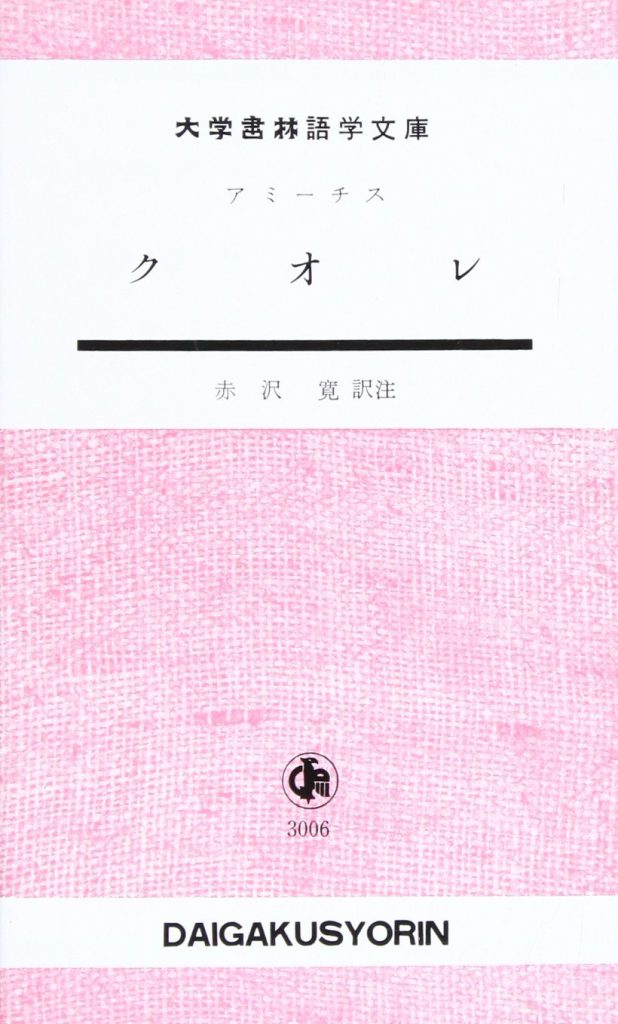
大学書林対訳文庫の『クオレ』は、そろそろ要らない本を一掃しようと整理していて見つけた一冊である。何時購入したのか忘れてしまった。イタリア語の読書に充てている週末の時間枠に、いつもの様にジョナサン(ファミレス)で今週土曜に試しに読んでみると、子供向けの内容で文章が易しいこともあり、思った以上に捗った。第2話目の「少年筆耕」に涙しそうになるが、よくよく考えてみると親父がそもそも軽率なのである。第3話目と4話目は読むかどうか未定。