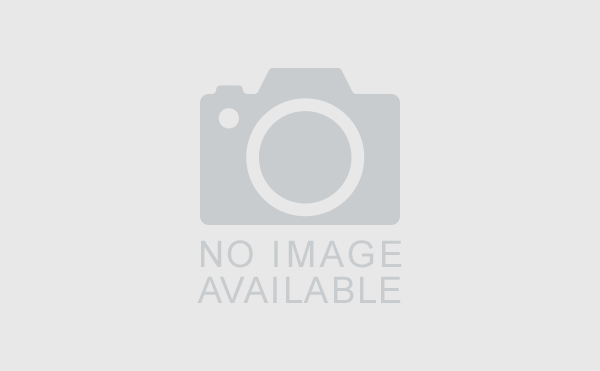デスチェアの殺人 ほか

近況報告的に。
この前、村上春樹のニュースを見て、ノーベル賞の季節かと気づいた。今年の文学賞は個人的にうれしい。知らなかった作家が受賞して、そのうち翻訳も出るだろうからだ。ハンガリー語にはちょっと興味があるので、読めもしない原書をKindleで探してみたけれど、まだ見つからなかった。
このサイトからしばらく離れていた。というのも、今月は漫画ばかり読んでいたから。Kindle Unlimitedで気ままに読み漁った作品はさておき、まずは『天地明察』の漫画版全9巻。これが実に素晴らしかった。すっきりとした絵柄も好みである。原作小説は読んでいたものの、内容をすっかり忘れていたので、新鮮な気持ちで楽しめた。
次に読んだのは『封神演義』の漫画版。ジャンプコミックで、たしか全24巻。原作小説を「二流」と断じた解説動画を偶然見かけ、その関連として漫画版に関する動画が勧めに出てきたのがきっかけとなった。ネットで全巻セットをほとんど送料程度の価格で入手し、夜ごとに数冊ずつ読み進めた。面白さは確かに理解できたが、読み終えた瞬間、費やした時間の分だけ損をしたような気がして、妙な後ろめたさを覚える。家に置いておきたいとも思えず、まだそれほど不要本が溜まっていなかったものの、段ボール数箱分をかき集めて一緒に売ってしまった。
先週はまるまる福岡へ出張していた。およそ二十数年ぶりの訪問である。久しぶりに歩いた福岡の街は、記憶の中の姿よりもずいぶん古び、幾重にも薄汚れた印象を受けた。主要駅も繁華街も概ね徒歩圏内に収まる便利さは変わらないものの、もう記憶の中の「好きな街」とは言えなくなってしまった気がする。天神にろくな書店が見当たらなかったのも残念だった。
唯一ありがたかったのは、二十四時間営業のマクドナルドがあり、朝五時から店内を利用できたことだ。夜を明かした酔っぱらいの大学生(?)が騒がしいのは玉に瑕だったが、それでも今回の滞在中は毎朝五時から、ホテルに朝食を摂りに戻る八時前後まで、広々と空いた店内に居座れたのは収穫だった。
最終日に半日ほど時間が空いたので、キャナルシティで『チェンソーマン』の映画を観た。テンポが良くて、話も『鬼滅の刃』よりずっと好みである。欧米でも人気らしいと聞いており、何より。ただ、どういうわけか見終わったあと印象に残るものが何も無い。『鬼滅』がいい意味でも悪い意味でも、後者の成分の方が多めではあるが、強く印象に残ったのとは正反対だった。
さて、表題の『デスチェアの殺人』。昨年の年末に一気読みした「ワシントン・ポー」シリーズの第六作目である。行きの便の搭乗三時間以上前に空港入りし、待合席で外を眺めながら腰を据えて読む。相変わらず読みやすく、物語への導入もスムーズでページが進む進む。飛行機を降りる頃には上巻をほぼ読み終えた。下巻はその夜と翌朝のマクドナルドにて読了。今作はシリーズの中でも最も陰鬱で、後味のスッキリしない物語であった。好みで言えば、六巻のうちでは五番手ほどだろうか。それでも、読者の好奇心をしっかりと掴んで離さない展開は、やはり見事である。

前から気になって目を付けていた『バイリンガルの壁』、出張中に発売日を迎えたので天神の書店、蔦屋書店だったかな、シャネルとナイキが一階に入っている建物の4階に入っている書店に行ってみたのだが、ここの在庫がまあ見窄らしいものだった。喫茶店と読書スペースが主体で書店はその付属といった感じ。岩波はどうやら置いていないらしい。博多駅まで出向くのも面倒だったので帰宅してから入手する。
斜め読みで一気に読み終えたため細部は拾いきれていないが、いかにも新書らしい内容である。つまり、どこかの一般読者の関心に沿ったテーマを、その分野の専門家が入門書として分かりやすくまとめたものだ。本書がどの層に響くかと言えば、子どもを英語バイリンガルとして育てたいと夢見る親たち、そして国際結婚や海外赴任などの事情から、実際にバイリンガル環境での育児に臨む親たちだろう。
バイリンガル環境で育つ子どもは、モノリンガルの子どもに比べて、それぞれの言語に触れる機会が相対的に少なくなる。そのため、どちらの言語の習得にも時間がかかる傾向がある。主言語の発達が遅れると、認知能力の成長にも影響が及び、就学期に必要な言語能力が十分でない場合には、そこから発展する学習言語(だったかな?)の獲得にも支障が出る。感情や情緒の発達の遅れも指摘される。
こうした点から、バイリンガル環境には利点もある一方で、ハンディキャップの側面が目立つように感じられた。それでも、現実にはバイリンガル環境で育児せざるを得ない家庭も多く、本書ではそうした場合に役立つ具体的なアドバイスが数多く紹介されている。
ただし、バイリンガル環境といっても導入の時期によって影響は異なる。主言語が十分に身についていない幼少期に第二言語を導入すると負担が大きいが、主言語が確立した10歳前後であれば、第二言語の習得はむしろ効率的に進むという。
念頭から離れなかった考えが一つある。これからの時代、「何語が使えるか」よりも、「どんな言語でもいいから(とは言え、現実的には生活環境に即した言語)、その言語でしっかり考え、表現できること」がますます重要になる気がする。多くの場合、それは母語だろう。学業や仕事などで必要となる言語は、後からでもどうにかなるものだ。