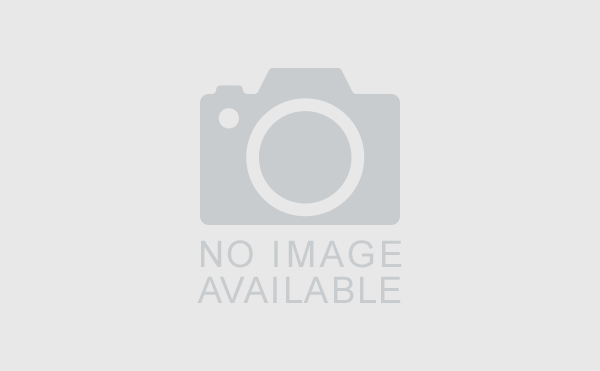日本語はひとりでは生きていけない
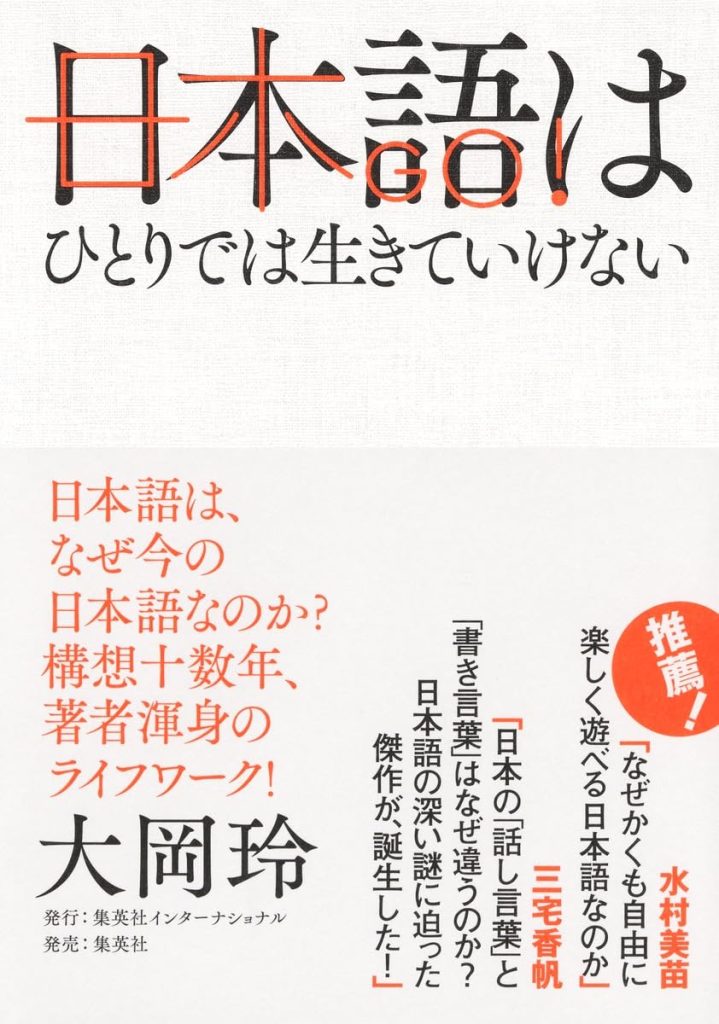
本とは関係の無い話から。先週末に、公開したての映画『鬼滅の刃』を朝一で観て来た。普段ならスルーするタイプの映画だけど、近所の映画館で全てのスクリーンが一つを除いてその作品に割り当てられており、妙に興味を引かれたからである。その感想はと言うと、アクションシーンはアニメーション技術の進歩や迫力ある演出に思わず見入ってしまうほど。一方で、頻繁に挿入される回想シーンの間延びしたテンポによって、作品としての一体感や緊張感に欠ける結果となったように感じられる。端的に言うなら白ける。何度か途中退席が頭を過り、トイレのタイミングでなどと考えていたらエンディングロールに辿り着いた。時折挟まれるコミカルな演出も作品のトーンと噛み合っていない要素である。が、そもそもこれらのミスマッチは原作に忠実であろうとした結果だろう。もっとも僕が『鬼滅』についてどれだけ知っているかと言えば、コミックを丁度この映画の箇所以降のみを読み、アニメ版は第一話と、遊郭編の後半話を観ただけ。要するにこの作品のファンではないのである。そんな個人の感想なので、悪しからず。これの続編は、その時の気分次第かな。
さて本題の『日本語はひとりでは生きていけない』であるが、この本はなかなか出会えないほど面白い日本語についての本である。日本語論をそれ程読んで来た訳でもない僕が思わずそう評したくなるくらいに、多くの示唆に富み、考えさせられる読書体験だった。タイトルから受ける印象よりは中身のしっかりした本だが、決して難しくはなく、価格も手頃なので、いずれ話題になるのではないかと思う。或いは既に話題になっているのかも?SNSを使わないのでよく分からないのである。
日本語は、他の、特に西欧系の言語(そっちの方の言葉しか僕は知らないので)に比べてルールがだいぶ緩い。本書で読むまで気付かなかったのだが、日本語には正書法が確かに無い。正書法とは、言葉を文字で表記する際の、統一された綴り方を意味する。そんなことないだろうと言う人は、日本語の表記法として漢字、仮名2種、近代以降はラテン文字があることを思い出して頂きたい。さらに、文字(主に漢字)の読み方も一通りとは限らない。更にさらに、同じ音声列が、しばしば多義的な意味を持つ。音声や書記体系のみならず、文法自体もどうやら緩いようである。これが原因かはたまた別の要因が関わるのか、日本語は移り変わり(流行り廃れ)が早いように感じる。とはいえ、アカデミー・フランセーズが言語の規範を厳密に定めているフランス語のような言語と比較してどうなのかは知らないので、あくまで個人的な印象に過ぎないのだが。そう言えばイタリア語の書き言葉は、確か現代語の手本となったダンテやペトラルカの文章(14世紀)からそれ程変化していないんだった。(なお、『新曲』を本当に僅かずつ読み進めているが、辞書に引っかからない言葉にしばしば遭遇する。恐らく活用等が微妙に異なるのだろう。)
この「緩さ」の故に、国の未来に強い危機感を持つ明治期の国士(誰だったかな?)が英語公用語化政策を打ち出し、後年には志賀直哉がフランス語を国語にしようと言い出したのであった。前者は兎も角、志賀はフランス語を知らず、唯の印象に基づく無責任極まりない発言だったそうな。だたし本人は至って真剣で、10年を経て記者に酒の席でその発言の真意を問われた際、なお立場をかえなかったそうである。両者に共通するのは、それぞれが提案した言語の問題(もし問題があればだが)に無知だったこと、つまり当時の日本語と比べての利点しか見えていなかったこと、加えて日本語の「緩さ」の利点が見えていなかったことである。志賀が「緩さ」を嫌ったのには彼なりの理由があるのだがそれはさておき、この「緩さ」の利点とは、言うまでもなく「あそび」の豊富さである。この豊かさの土壌の上に和歌・俳句をはじめとする言語芸術が斯くも発達し、現代に於いてはJ-popで面白い歌詞表現が作られる、そうな。J-popはあまり知らないので鵜呑み。
それでは日本語の「緩さ」は何処から来たのか、これに答えたのが本書である。この経緯には深いふか~い背景が有り、それを僕がここで手短に説明するには余りに荷が重い。実は表層的な要約は最後の方の章に記されているのだが、気になる向きは是非全編をご自身で読み進めて頂きたい。読んだなりの充足感が得られると思う。本書は多数の先行文献を引用していて、要所要所の読書案内としても有難い。例えば『日本語が亡びるとき』には簡潔な要約が示されているものの、僕自身は内容の方をすっかり忘れており、再読したくなった。