劉邦と項羽と劉邦

宮城谷昌光の『劉邦』中巻をつい読んでしまった。お話は、秦の大軍から趙を開放するために項羽は楚王である懐王(王孫という触れ込み)の元から僅か数万の手勢を率いて北上し、劉邦は関中入りを目指すところまで、で中巻は終わり。展開が少し遅いように思われる。この後が結構長いのだ。関中に一番乗りした者を関中王にするという懐王のお触れが出ている。劉邦は南方に転戦して武関から関中に入り、佞臣の進言により函谷関を閉じ、項羽と対決する姿勢を見せる。一方の項羽は秦軍を破って関中に猛進し、函谷関を打ち破る。窮した劉邦は「鴻門の会」を経て項羽と表面上和解する。説明不要とは思うが、関中とは大雑把に言えば戦国期の秦国領を指し、肥沃な渭水盆地を山岳地が取り囲む。この地の利が秦国の国力が強大になった要因の一つであるらしい。
漢中王に任ぜられた劉邦は関中を項羽に明け渡し、秦嶺山脈の麓、漢中平原へと向かう。四川省にも近い(含む?)僻地中の僻地である。途中で彼は踵を返し、関中を恣に略奪して東方に退いた項羽の後を追うように再び関中に入る。ここに両者の対立が表面化する。この後が色々ある。劉邦軍の大将軍韓信は本体とは別に軍を率い、天才的な軍略で各地を転戦する。劉邦は項羽と戦うたびに敗退し、両者は広武山で1年間睨み合ったりするのだが、残るは下巻一冊のみ。このペースで垓下の戦いまで辿り着くことができるのだろうか。因みに、この漢中王の「漢」をもって王朝名が「漢」と決まり、「漢」民族や「漢」字に受け継がれた。それ以前は「華夏」が民族の自称名であったそうだ。「漢」民族の旧称である。さらに因むと、統治領名を王朝名とするのが王朝命名の伝統だそうだが、この法則を破ったのが「明」であるらしい。
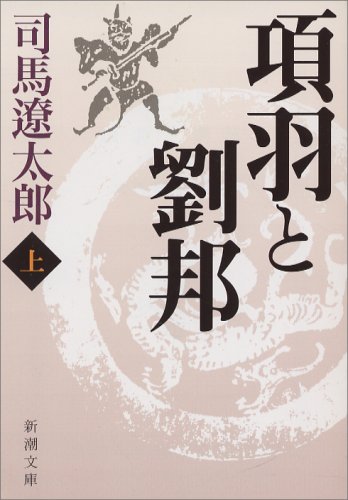
僕は宮城谷の柿ピーの様に単調な描写が好きなのだが、本作では君子然として描かれる劉邦に人間的な面白味を感じることができなかった。彼の部下達も小君子が多く、例えるなら、よくできたのび太君がキレイなジャイアンやキレイなスネ夫達と冒険する映画版ドラえもんを想像すれば本作の雰囲気がどういうものかが分かると思う。下巻は読む積もりはない。
代わりに司馬遼太郎の『項羽と劉邦』を読んだ(下巻の最後一章がまだ残っている)。多分3度目くらいの読書である。上の粗筋は『項羽と劉邦』のものであった。こちらの劉邦は空虚な大器(大きな器)である。つまり彼自身に実務力は無いが、周りの人が世話を焼いてくれる、そういう一種の好愚者として描かれる。本書から一節を以下に抜き出してみる。「沛公(劉邦)は、まれにみる長者だと誰もが言う。長者とは人を包容し、人の些細な罪や欠点を見ず、その長所や功績を褒めて常にところを得しめ、その人物に接すると何とも言えぬ大きさと温かさを感ずる存在を言う。この大陸でいうところの、徳という説明しがたいものを人格化したものが長者であり、劉邦にはそういうものがあった。言い換えれば、劉邦の持ち物はそれしかない。」馴染んでいる所為もあり、この劉邦像が好きである。
両著者を同時に読むと良くわかる。司馬遼太郎の想像力は逞しい。彼の味付けは、物語の全てを一様にソース味へ変えてしまう。ピリッとした濃厚味がクセになるのである。その内に飽きが来る味ではあるのだが。

