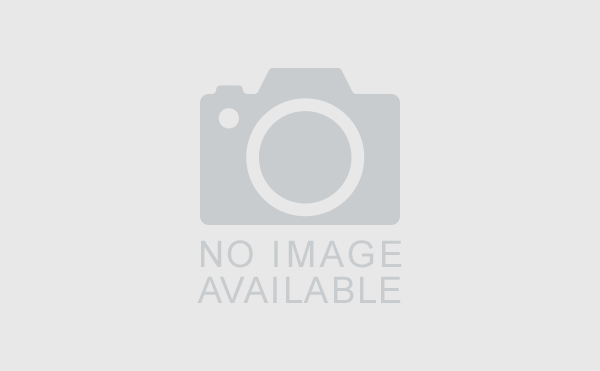デンマーク語入門: 文法、練習問題、テキスト訳注、語彙 (近代文芸社新書)
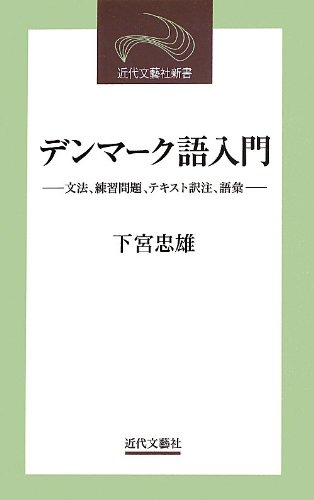
『魔の山』をようやく一割ほど読み進めた。『トニオ・クレーガー』を読んだときから感じていたことだが、原書を辞書を引きつつじっくり読み進めると、日本語訳で読むよりも理解の細やかさ、あるいは没入感が格段に高いことに気づく。おそらく「マインドフルネス」の度合いが違うのだろう。もちろん誤解している部分も少なくないはずだが、場面ごとの把握に重きを置き、読む速度を二の次にしていることが大きく作用しているのだと思う。
一方、『神曲』は『魔の山』の陰に隠れて最近は手が伸びず、むしろ義務感を覚えるようになってしまった。そこで代わりに『百年の孤独』を読むことにした。かつて日本語で一度読んだきりで内容もほとんど覚えておらず、文庫版の刊行を機に改めて読み直そうと思っていたからである。ただしスペイン語には長らく触れておらずすっかり忘れてしまっているため、この二週間ほどは就寝前の読書として、Kindle Unlimitedで読める初級向けの読み物を二冊ほど選び、ウォーミングアップに充ててきた。
そして今週末から、いよいよ目標の本を読み始めてみたのだが、語彙のレベルが高く、やはり容易には進まない。それでも言葉のリズムには独特の心地よさがある。喫茶店で周囲に人がいないときには、口の中でぶつぶつと呟きながら読んでしまうのだが(これはドイツ語の際も同様)、その響きはイタリア語よりも自分の好みに合っている。アプリ版の辞書を片手に、動詞の活用形も復習しつつの読書なので、まだ進捗はせいぜい1%ほどに過ぎない。
母語話者でなければ聞き取りや発声が難しい音があるわけでもなく、発音で迷う場面もほとんどない。文字を見たまま素直に音に置き換えればよく、文法的に特別込み入っているわけでもない。もし近現代史の帰結を覆して、「習得のしやすさ」を第一の条件として国際共通語を選ぶことができるなら、スペイン語は英語よりもはるかにふさわしい言語だと思う。
さて、最近寝る前に少しずつ読んでいたのが表題の『デンマーク語入門』である。これは何年も前に購入して棚に眠らせていたもので、新書サイズで内容は決して詳しくはないが、言語の特徴を概観するにはかなり優れている。「読んでいた」とはいっても、後半の読み物部分はまだすべてを読めていない。あわせて『デンマーク語基本単語2000』という単語帳もぱらぱらと捲ってみたが、こちらは正直、発音も確かめたい今の僕にはあまり役立たない。というのも、一応カタカナで読み方は記されているものの、日本語よりも遥かに多い母音を区別するデンマーク語において、「ア」や「エ」がどの音なのか判然としないのは困るのである。発音に迷いが無くなったらその時にまた。その点、『デンマーク語入門』巻末の語彙集には発音記号が付されており、単語帳としてもむしろこちらの方が優れていると感じる。さらに良いのは、YouTubeで見つけたデンマーク語学習チャンネルの「日常単語20」や「日常単語40」といった動画である。繰り返しゆっくりと発音してくれるうえ、口の形も確認できるので、音の理解が非常にしやすい。
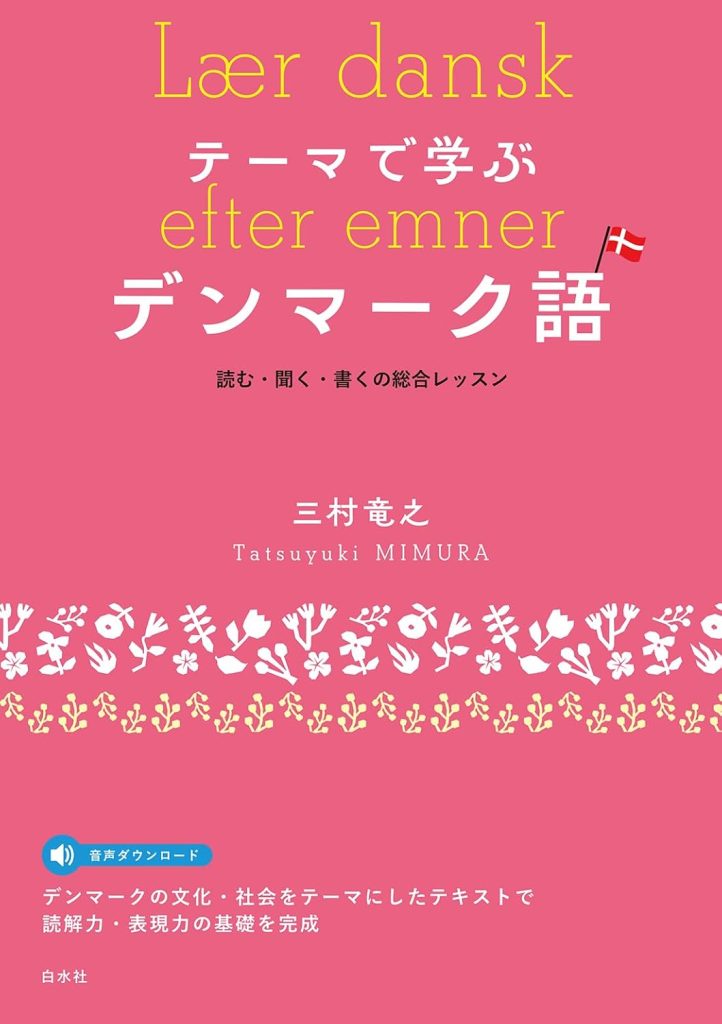
表題の本を読み終えたら、次は『テーマで学ぶデンマーク語』だろうか。デンマーク語をやってみようかとふと思い立った際に真っ先に購入した一冊なのだが、リスニングの冒頭の段階で早くも耳が追いつかず、挫折してしまった。なお、デンマーク語で読めるものは割と有るようで、その水準にまで学習を続けられるかどうかはともかく、読めるものがあるという事実はモチベーションに直結するため、非常に大きな意味を持っている。