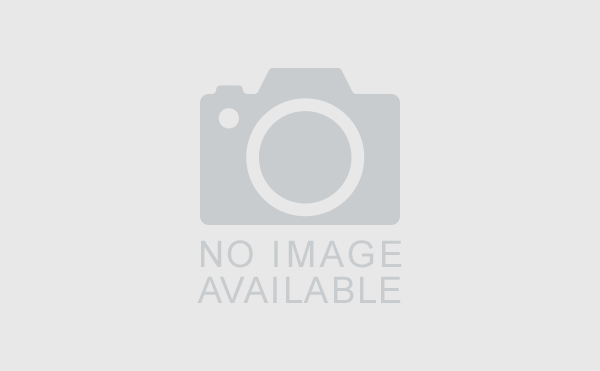インド哲学 七つの難問
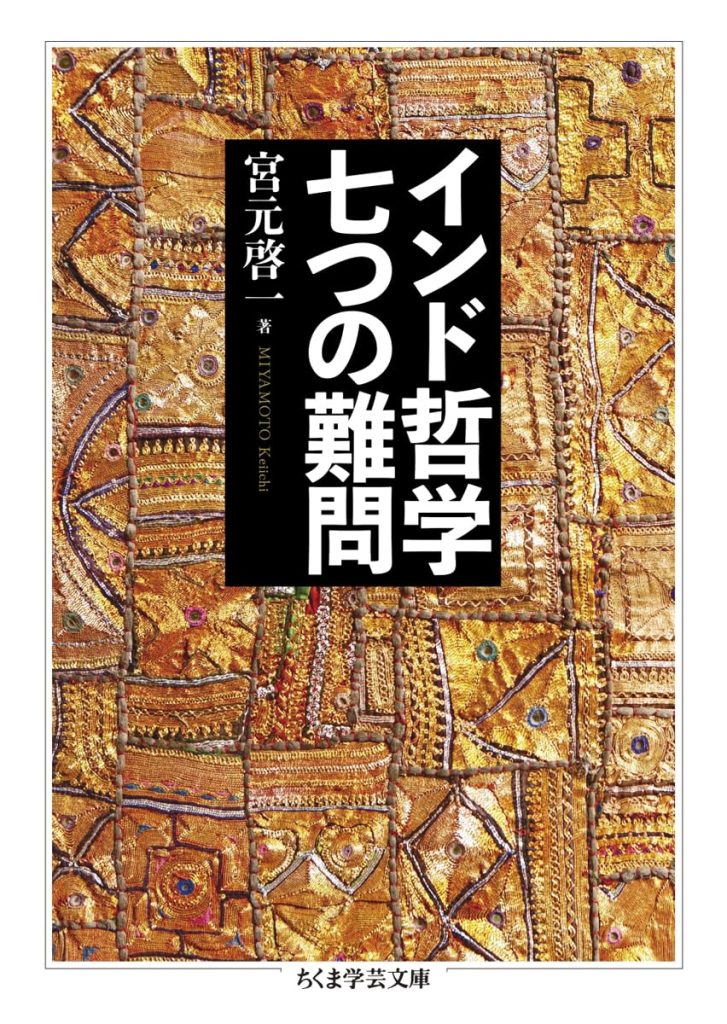
最近、書店の中を一巡りする度に目を遣って確認してしまう小説があり、韓松の『無限病院』と楊双子の『台湾漫遊鉄道のふたり』の2冊がそれ。特に前者の方は「このSF小説がすごい」に続きそのホラー小説版でもランキングに入っていて、読みたい新刊書等が途切れた際には優先的に読みたいと思っていた。今が丁度そういうタイミングである。果たして今現在はSFを読みたいのだろうかと自分の気分を探りながら書架を眺め歩いていると、柚木麻子の『BUTTER』文庫版が平積みされているのが目に飛び込んできた。海外で高評価を受けているとのニュース記事を暫く前に見て以来気になっていたこともあり、気分はこちらに傾く。今晩から読み始めるつもりだが、もし気に入らなかった場合は、どうしようか。因みに今、Kindle版が半額なのである。
さて表題書の『インド哲学、七つの難問』、これは評価に困る本である。哲学、特に「インド」哲学の部外者を対象とした解説から始まるものの、部分部分(本書全体の約3分の1くらい?)に於いて部内者向けの議論が展開されるからである。冒頭で著者は哲学(哲学研究自体も哲学である)を、自分で飛行機を飛ばす行為に例えている。ところがインド哲学研究では、西洋哲学と異なり、飛び立つための滑走路(つまり先行思想や文献)がまるで整備されておらず、専ら滑走路整備(文献学的研究、或いは地域研究)の専門家として安住するきらいがあるそうな。そうした潮流から抜け出し、著者自身で初飛行を試みたのが本書になるらしい。そんな訳なので部内者向けの議論が展開される点に関しては了承していた。ただ、一通り読んではみたものの、良く分からないので面白くないのが問題なだけである。一言断っておくと、部外者向けの箇所は面白かった。
議論されるテーマを順に挙げれば、「ことばには世界を創る力があるのか?」、「「有る」とは何か、「無い」とは何か?」、「本当の「自己」とは何か?」、「無我説は成り立つか?」、「名付けの根拠は何か?」、「知識は形をもつか?」、「どのようにして、何が何の原因なのか?」の七つ。なかなか興味深い議題が並ぶ。簡単なものから順に、章が進むにしたがって難しくなるという話である。しかしながら、例えば六つ目の「知識は・・・」は一般知識で議論の筋を十分追えるので分かり易いと思う一方で、5つ目の「名付けの・・・」は丸々がインド哲学の知識内で議論されており、かなり退屈(勿論理解できないので)である。
面白かった話題で短いものを一つだけ紹介すると、インド哲学における「無い」の考え方。西洋哲学では、または多くの言語では「〈対象となる何か〉が無い」と表現するところを、インド哲学(サンスクリットでも?)では「「無い」が有る」と考える(「〈対象となる何か〉において「無い」が有る」かな?)。これは零の概念そのもの。なお、この表現が矛盾なく機能するためには、詰めておかないといけない幾つかの前提が有るように思えるのだけど、それはそれ。
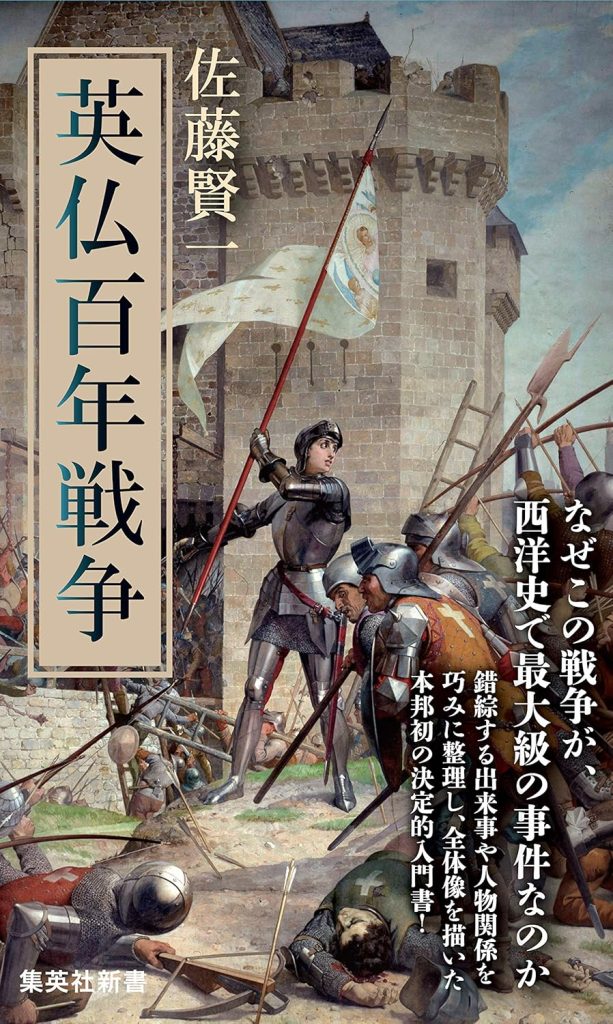
『英仏百年戦争』はkindleライブラリ内の積読書である。著者の小説は以前に2,3冊読んだものの、文体が僕の好みと微妙に嚙み合わず、以来敬遠気味になっていた。何か癖がある訳でもなく、一文一文は決して読み辛いわけではないのに、纏まったものを読むと流れが途切れ途切れに感じてしまったのである。歴史解説書である本書ではそうした読み辛さは全く感じなかった。難点があるとすれば、私見が山盛りで記述が軽快過ぎること。日本人には馴染みの薄い百年戦争史を楽しい読み物として紹介したという意味で素晴らしいと思う。
百年戦争とはフランス人同士が領土と王位を争った戦争であった。一方はフランス王家。もう一方はフランス王を君主とする封建領主で、もちろん血縁的にもフランス人である。後者はイングランドの王位も継承していたが、当時イングランドは辺境国に過ぎず、アイデンティティの主体はフランスの領主なのであった。婚姻関係や同盟で他の領主を取り込みつつ、この両者が一進一退の攻防を繰り返す。最終的には戦争の舞台であったフランスの地方領主が貧窮して勢力を喪失し、フランス王家に権力が集中する。同様にイングランドでも、百年戦争敗戦の結果に伴い、王位継承をめぐる薔薇戦争が勃発するが、有力領主が没落してイングランド王の一人勝ち状態になる。地方領主が分立する中世的な封建体制から、中央集権国家が誕生するのである。
それまで中世ヨーロッパの主役はローマ教皇と神聖ローマ帝国皇帝であった。百年戦争を経て、イングランド王とフランス王が台頭し、現代まで続く国民国家の先鞭を付けることとなった。これが百年戦争の歴史的意義である。(以上、全て本書を参照。間違いが有れば全て僕のミスである。)