死に山

1959年冬のソ連にて、大学生の登山グループ9人がウラル山中で遭難した。下山予定を過ぎても帰還報告が無いことを心配したメンバーの身内が大学に問い合わせ、救助隊が派遣される。彼らが山の斜面に発見した、彼らのものと思われるテントは部分的に積雪で潰れてはいたものの、中は直前まで人が居たかのように整っており、無人である。やがてテントから幾分離れた箇所で雪に埋まった数人の死体が発見されるが、彼らは裸、或いは部分的にしか衣類を身に付けておらず、凍死であった。さらに時間が経ち、全く異なる方角の川床で残りのメンバーが発見される。一人の遺体からは舌が欠け、体の一部が不自然に変色しており、放射能も検出される。更にこの遭難事故が発生した頃、発光体を伴う天体現象が観測されたとの報告もあった。半世紀のち、この不気味な事故を偶然に知ったアメリカのテレビ製作者(本書の著者)が現地に赴いて調査をする、という粗筋である。
実際に何が起こったかについて知ることはできないが、かなり納得のいく推測がなされている。僕も読みながら何が原因だろうと考えていたけど、これは思い至らなかった、というよりも僕の知識には無かった。本書の構成は、登山グループの行動を文書等から想像で補って描写した事故パート、事故報告書等と聴き込みから構成された捜索パート(いずれも1959年)、著者自身が直接ウラル地方に行って調査した調査パート(2012年)、と場面が頻繁に切り替わる。少し落ち着かない構成ではあったが、なかなかの力作ノンフィクションだと思う。アマゾン風の採点だと星4つ。本書と同時に、日航機事故を調査したノンフィクション(タイトルは何だったかな?)も購入したのだが、著者が当事者と近い関係だからだろうか、被害者へ配慮したであろう文体が妙に読みにくく感じてしまい、未読のままである。
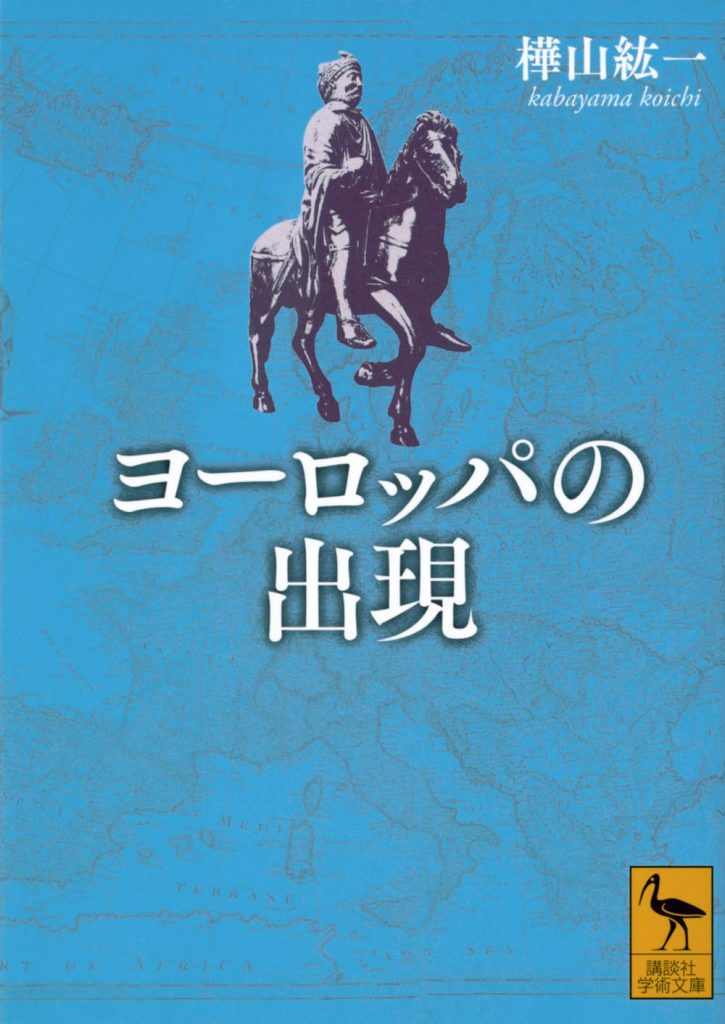
表題書の後、目を付けている本が書店に並ぶまでの場繋ぎとして読んだのが『ヨーロッパの出現』。歴史を通したヨーロッパの立ち位置を概観した本で、かなり薄い内容。言いたいことは特に無し。

