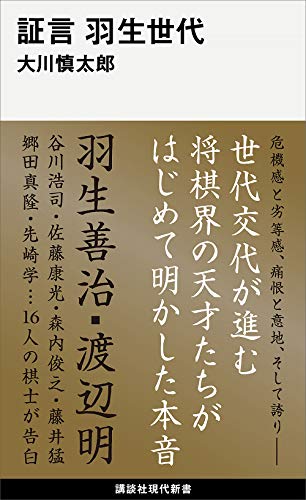ドリトル先生と月からの使い
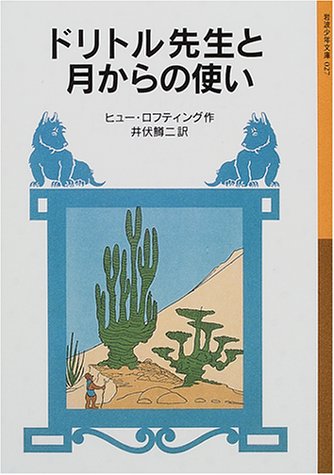
子供の頃に読んだ『ドリトル先生航海記』は僕の大好きなお話なのだが、シリーズの他の本はこれ迄キチンと読んだことが無かった。大人になって一度だけ、シリーズの第1巻目『アフリカゆき』を手に取ってみたものの、著者の動物知識のいい加減さにに呆れて途中で放り出し、以来、気になりつつも書店では表紙を眺めるのみであった。岩波少年文庫の表紙デザインは雰囲気が有り、ついそちらに目を遣ってしまう。少々フォローしておくと、著者は生物学を含む科学分野の方面の専門家ではなく、20世紀前半に活躍した児童文学作家なので、現代の知識や常識で彼の知識を論うのはフェアではない。言葉使い(差別表現など、井伏鱒二の翻訳も含む)に関しても同様である。
つい先ごろAmazon Unlimitedに、具体的には書かないが別出版社の別翻訳者によるドリトルシリーズ全巻が入っているのを見つけ、『郵便局』を読み始めてみたところ、どうにもしっくり来ず、僕の持つ「ドリトル像」からのズレを意識してしまった。そこで慣れ親しんだ井伏鱒二訳の岩波版を購入した、というのが約二十年ぶりにドリトル先生を読み始めた次第である。第7巻目の表題書を最初に選んだ理由は特になく、敢えてに挙げるとすれば突飛な内容を期待したからであった。
本書は二部構成であり、短い第一部目は月と関係は無い。先生の庭に設けられた動物園に付属する「雑種犬ホーム」の博物館館長ケッチ(犬)が自身の来歴を犬の集会で語る、という内容。雑種犬ホームとは純血種でない故に行き場所を無くした犬たちの安息所である。余談になるが、僕は「ミックス犬」という言葉にある種の気持ち悪さを感じる。既存の「雑種」を言い換えることで、それに付随する負の印象を覆い隠したいというペット業界の下品さを背後に見てしまうのだ。意図せず雑種が生まれるのは概ね飼育者の怠慢と、それを処分できないいい加減さが原因である。そういう事情を言葉を挿げ替えて覆い隠すべきでは無いと感じるのである。ブリーダーではなく、品種の保存を気にしない人もいる。そういう人にとって、「雑種」は別段負の印象を纏わない筈である。つまり、「雑種」という言葉を堂々と使えば良い。付け加えると、新しい品種の多くは既存の品種間の交雑で生まれる。本書の第一部にはその一例がチラと登場する。
第二部で先生は虫語の勉強を開始し、様々な虫との会話を試みる。そんな中、家ほどもある巨大な蛾が庭を訪れる。そして、と話が続く。日本語のタイトルはこの第二部のみを言い表していて、一部・二部を通すと英語タイトル”Doctor Dolittle’s Garden”の方がより相応しい。子供向けの本は寝床で読むには丁度良く、このシリーズはもう暫く読むつもりである。月世界での冒険は次巻、『ドリトル先生月へゆく』で語られる。
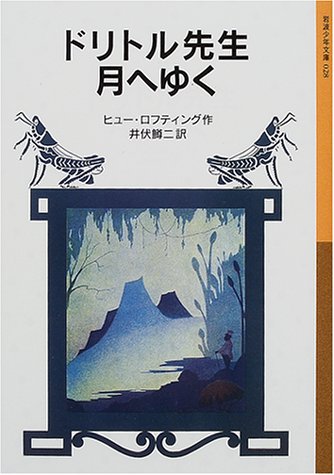
表題書と同時に、講談社現代新書から少し前に出版された『証言 羽生世代』も寝床で読んでいた。将棋の羽生さんと同世代、前後世代の棋士全16人へのインタビュー集である。彼らの殆どが第一線を退いた今、なぜ羽生と羽生世代があれ程強かったのかがライバルの視点から証言される。長年に渡って将棋タイトルの殆どが、羽生と彼と同世代のライバルたちに独占されていたらしい。将棋に興味がなくても面白い話であった。ただ、似た内容の繰り返しなので途中で飽きる。本書に関してこれ以上紹介するつもりは無く、表紙を載せるだけ。