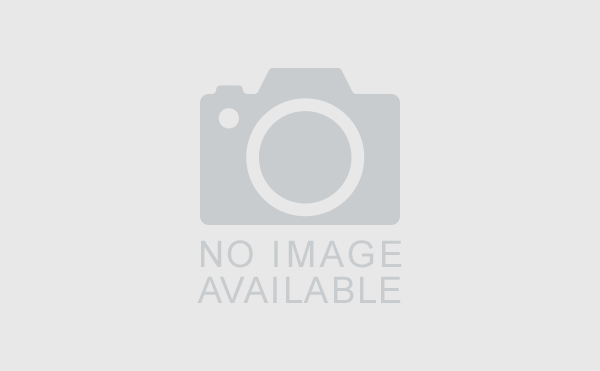アッシリア全史 他
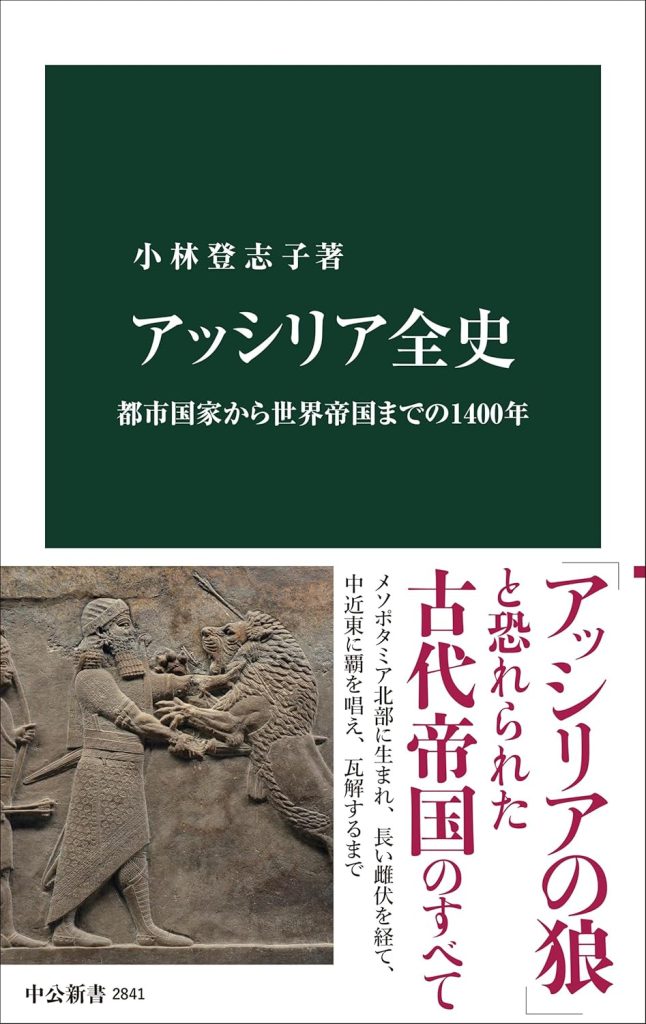
読んだ本の紹介と一口コメント。先ず『アッシリア全史』は馴染みの薄いアッシリアの長い長い歴史を一冊に、ポイント毎に簡略に纏めたという内容。都市国家として誕生したアッシリアの治世は、独立を果たした約前2000年から前609年の滅亡までの1400年間、117代の王に及ぶ。上下巻に分かれても良いのでもう少し詳しい記述が有っても良かった。続いて読んだ『ユダヤ人の歴史』は最初の三分の一が古代と中世、残りが近現代という配分。近現代に入ると興味を維持するのが辛くなる。
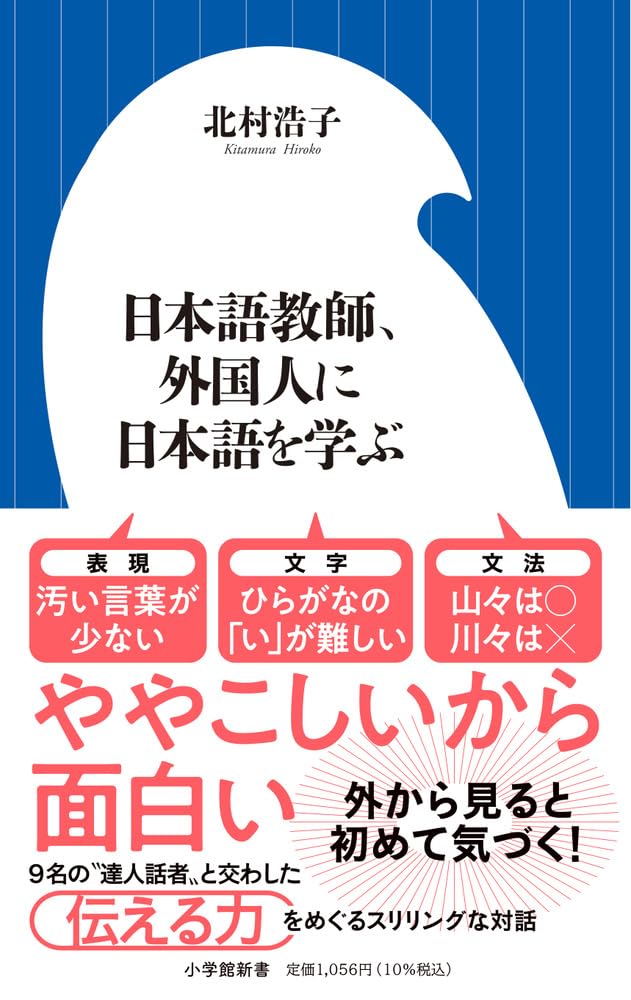
『日本語教師、外国人に日本語を学ぶ』はタイトル買いの一冊。日本語に熟達した外国人たちへの問答集。動機や勉強法、言語としての印象など。当然ながら何を母語とするかによって日本語の印象は異なる。共通するのは、会話で意味の通じる遣り取りをするだけなら難しくはない、という点だろうか。ただしTPOをわきまえて日本人らしく会話するには、文化(能などの「文化」ではなくて、日常的な文化のこと)も知っている必要があってとても難しい、と口を揃える。つまり言外のニュアンスが大切ということである。個人的に面白かった例をもう一つ;フィンランド人の話では日本語は個人的な感情を伝えやすいと言う。一方でジョージア人によると、日本語は罵倒や賞賛をするための言葉に乏しく、感情を吐き出すための言葉を探すのに苦労するという。一見真逆な様でいて、何か一つ要素を挟むだけで同じことを言っているような気がする。それが何か未だ思い付けないで居るが、何だろう? 本書に関しては他にも(もっと?)興味深い話が多々有ったのだが、割愛。
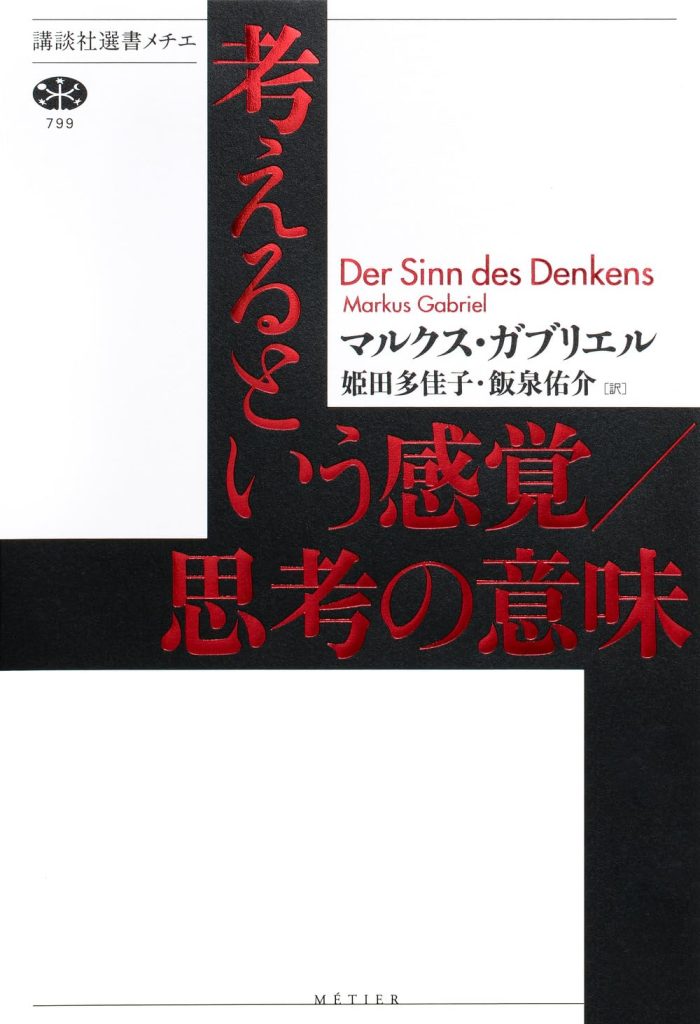
『考えるという感覚/思考の意味』は難しく、同時にとても楽しめた一冊だった。詳細な感想は、もし纏めることができるようであれば別の機会に。思考とAIに興味が有る人は興味を持って読めると思う。
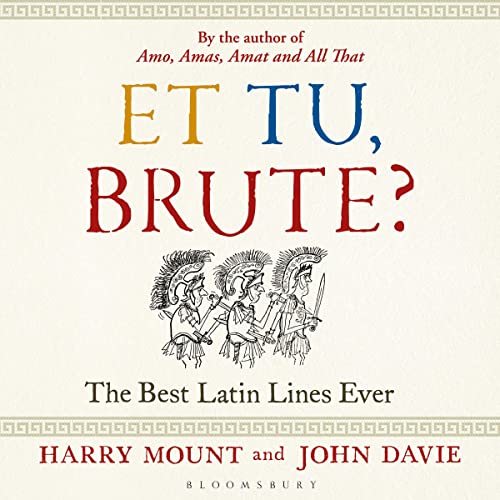
Audibleで聴いた “Et tu, Brute? The Best Latin Lines Ever” は中々良かった。特に最終章、慣用句とその解説がアルファベット順に40分程度で読み上げられ、この個所は繰り返し聴いた。そうそう、この「良い」や「面白い」等の評価を伝える言葉も日本語には乏しいそうな。僕自身も高頻度で「良かった」「面白かった」とばかり書いていると自覚がある。
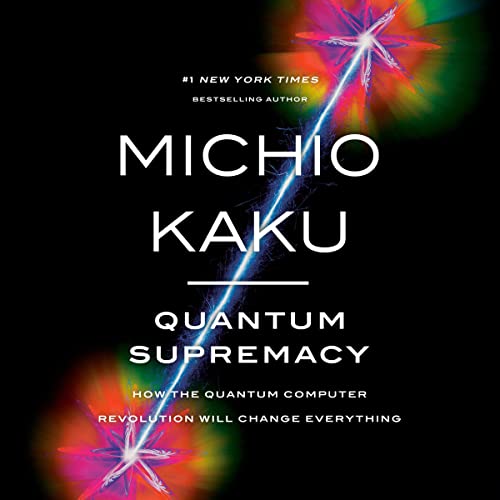
“Quantum Supermacy” は量子コンピューターの性能とその背景知識を簡単に紹介したもの。分かり易いけど、説明がやや回りくどく感じる。ところで、かつて量子コンピュータと並んで名前を聞いていたDNAコンピューターはどうなったのだろうか。