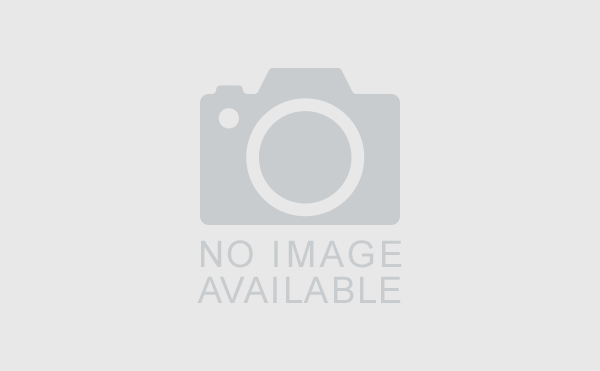ブラックホールは白くなる 他
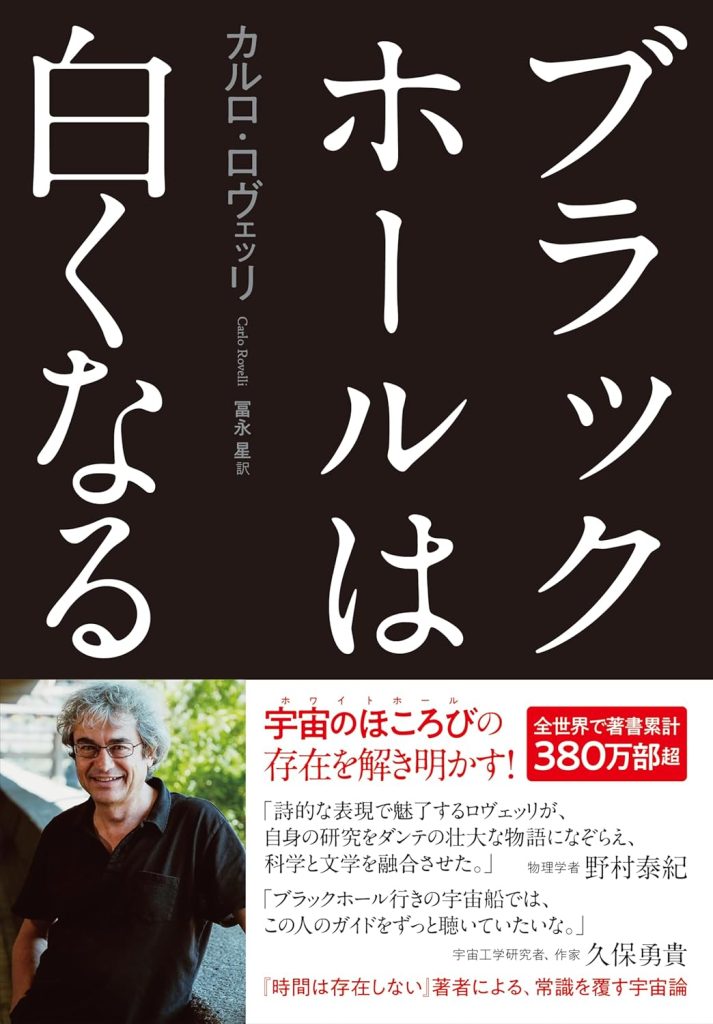
非常に面白かった本3冊(一冊は読み始めたばかりであるが)の紹介で、先ずは『ブラックホールは白くなる』から。このカルロ・ロヴェッリの新刊は、2ヶ月ほど前に購入して、ずっと放置していた。どうも僕にはこの癖があって、書籍に限らず本命はいづれ手を出すことが分かっているので後に回し、2番手以下を優先しがちである。そのまま忘れたり億劫になることもあり、決して良い癖ではない。今回もようやく重い腰を上げて、いや満を持して読んだ本書は、やはり素晴らしく面白かった。 相対性理論と量子論の融合を目指す2大理論である「ヒモ理論」と「ループ量子重力論」、その後者における第一人者である著者の科学啓蒙書はいずれも、物理学から理論的に導かれる物理的世界(あくまで仮説に基づく話ではあるが)の一端を、一般読者にとって素晴らしく分かりやすい様式で示してくれる。これらの著書がさらに特異なのは、ただの解説書の枠を超えて文学作品に昇華している点である。
本書では、彼の学生が抱いた着想から始まった、ブラックホールとホワイトホールについての彼らの研究成果を巡る旅が、著者の内省を交えつつ語られる。旅の道連れはダンテである。『新曲』は地獄の深層へと深いすり鉢を下り降りていったダンテが、煉獄を経て、天国へと上昇する物語であり、ブラックホールへと落ちていく観測者がこれに重ねられている。百数十ページと少ないボリュームではあるが、中身は濃い。なお、彼の前著作にも共通する点として、決して退屈ではないのに寝床で読んでいると不思議と眠くなってくる。リラックスできるからかも知れない。
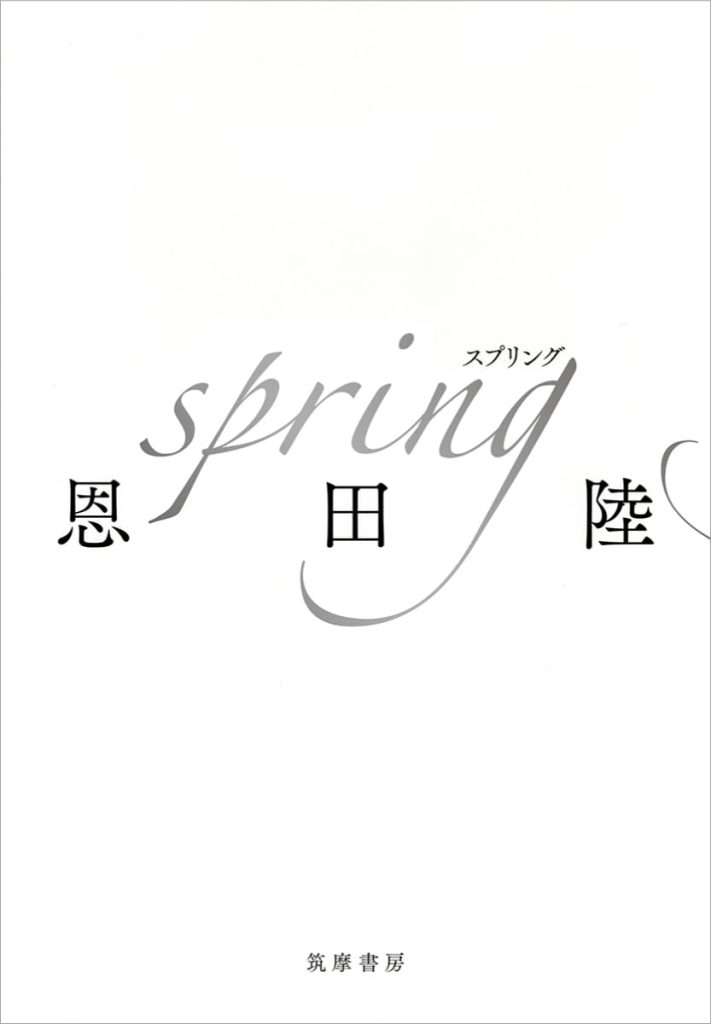
『spring』は衝動買い。書店をブラブラした際、本屋大賞入賞作品の平積みにふと目を遣ると、「バレエ」と言う言葉が飛び込んで来て、著者の作品の中で唯一覚えている『蜜蜂と遠雷』が頭を過った。あれは爽やかで胸が熱くなったなあと思い出し、天才少年の成長を描くらしい本書も同じように面白いのだろうと期待して読んでみたのだが、結果はまさに期待通り。浮世離れの天才である主人公「春」の成長と活躍が、彼の人生と深く関わった四人の人物の視点から第三者的に語られる。創作者の俯瞰的な視点からの描写と比べると、描写範囲が語り手と「春」が交わった場面のみに限定され、さらに語り手の擬似主観的なフィルターが挟まれることになるが、これが作品に臨場感や瑞々しさを与えていると感じる。なお、語り手の四人目は「春」自身である。そこでの独白から、彼は決して浮世離れしているわけではなく、「一般的世間」に馴染むことができない苦悩を抱えた少年・青年像が浮かび上がる。
この種の娯楽小説を読む際の常として今回も先の展開を予測しながら読んでおり、主人公の名前からして、あの曲が最後に来るだろうという予想それだけは当たった。そもそも先の展開が気になる類の物語展開がなく、ただ場面場面で描かれる主人公の逸話を楽しむ小説である。ダンサーとして、また同時に振付師として異彩を放つ彼のような才能は例え小説としてもやり過ぎでは無かろうか、と思い現実を振り返ると、居た。ロヴェッリと大谷。探せば他にも無数に居るはずだけど割愛する。
本書を料理に例えるならオムライス。たまに食べる分には美味し良いけど、適度にしつこく単調で飽きもするので食べ続ける気分にはなれない。本書が本屋大賞の6位に甘んじたのも納得がいく。個人的採点は5点満点の4点ど真ん中。著者の本は片手で数えるくらいしか読んでいないのでこれを機に手を出してみたい気持ちはあるのだが、少なくとも数クッション挟んでからになるだろう。次は『愚かな薔薇』が妙に気になっている。本屋大賞繋がりで『フォースウィング』もやっぱり気になるものの、続刊の分厚さに気押される。
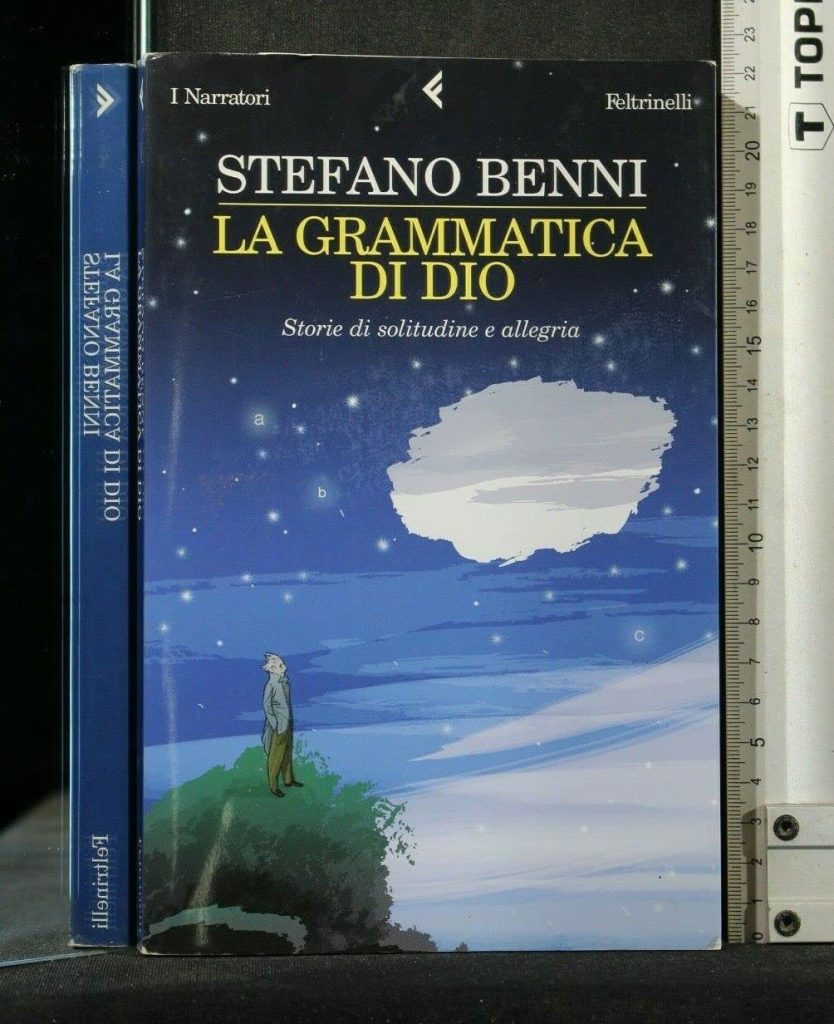
“La Grammatica Di Dio” は先週末から読み始めた、イタリア人作家の短編集。孤独をテーマにしているらしい。まだ二話目を読んでいるところであり、一話目の”Boomerang(ブーメラン)”が妙に面白かった。妻を亡くした男が、突如飼い犬のブーメラン(名前)のことを嫌いになり、捨てに行ってもその度に犬が帰ってくる、というお話。知らない単語だらけで辞書アプリは手放せないが、それでも同時に辞書を片手に読んでいるトニオ・クレーガーと比べると格段に読みやすい。面白いと感じる理由は、拙い言語でもあまりストレス無く、ゆっくり速度を落として読めるからではないかと思う。
それにしても、ドイツ語の文章(と言うよりもトマス・マンの文章かな?)にはどうしてあんなに冗長と感じる単語が多いのだろう。それらにしても、微妙なニュアンスを伝えるためには必要なのだろうが、曖昧さを残さず書き表すところがドイツ語らしいと言えるのかも知れない。それで思い出したが、カフカの『変身』は何だか曖昧な表現が多かった。またカフカを読みたくなってくる。さて、イタリア語の読書で困るのは、欲しいと思う本の多くは日本のアマゾンに置いていないところである。イタリアのアマゾンで注文するとなると送料が高いし。