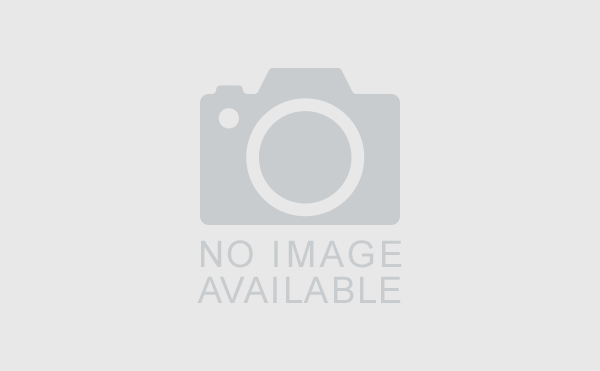8週間語学の旅 水先案内人はずれっちと様々な言語の海へ
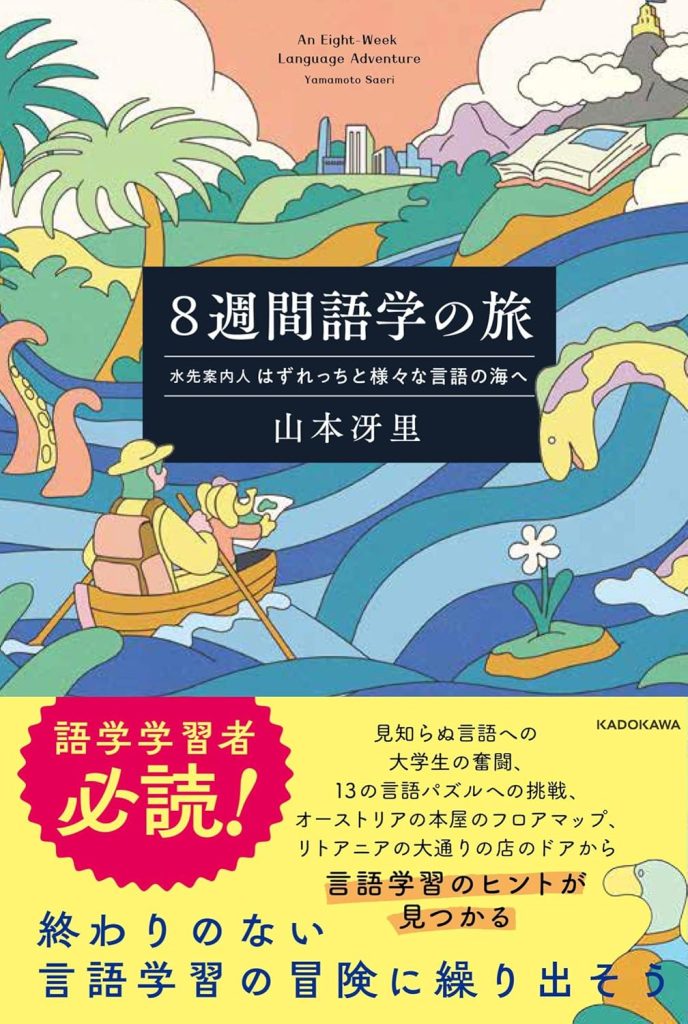
この一週間は、また読書の時間のほとんどを漫画に費やしてしまった。まず手に取ったのは『それでも町は廻っている』全16巻。全巻Kindleで揃えてあるものの、10巻以降は一度しか読んでおらず内容もほとんど記憶に残っていなかったため、新鮮な気持ちで楽しむことができた。連載当時も「これは面白い」と感心しながら読んでいたことを覚えているが、特に時系列を入れ替える手法は強く印象に残る。改めて通読してみると、当時は気づかなかったが、絵柄や作品の雰囲気が初期から少しずつ変化していくのがよく分かる。もう一度読み返したい気もするが、その分活字の本を読む時間が減ってしまうので、しばらくは我慢しておくことにしよう。
二つ目は『ヴィンランド・サガ』の前半数冊と最終巻。昨日、最終巻となる第29巻が出たと知り、すぐにKindleにて購入した。農場編が完結する15巻あたりまでは読んでいたが、それ以降は断片的に拾い読みしただけで、特にアメリカ大陸編にはまったく手をつけていなかった。そんな状態でいきなり最終巻を読んだので、主人公以外はほとんど知らない登場人物ばかりだったが、それでも十分に満足できる結末にたどり着けて、本当に良かった。Kindle版も飛び飛びでしか揃えていないので、とくに未読部分は今後少しずつ補っていきたい。この気持ちが続けばの話だが。それぞれどんな漫画なのかは省く。
そして、この一週間で唯一読んだ文字の本が『8週間語学の旅』である。著者は山口大学の教員で、自身が担当する語学クラスの概要を綴った内容。授業では、受講者がそれぞれ好きな外国語を一つ選び、8週間かけて少しずつその言語に馴染んでいく。この手の独学に慣れていない学生でも迷子にならないよう、週ごとに目標が設定されている。さらに、日本語話者にとっての言語の難易度によってゴールの到達度も調整される。例えば、日本語と比較的距離の近い朝鮮語や中国語であればこのレベルまで、ラテン文字を使うので読み書きに負担が少ない言語であればこのレベルまで、そして文字の習得を一から始める必要がある言語であればこの程度まで、といった具合である。
このように楽しそうな授業を実際に受けられるとは、羨ましい限りである。読みながら、自分だったらどの言語を選ぶだろうかと考えるのも、なかなか楽しかった。僕の場合、こういう機会には、独学ではなかなかやる気が続かないものや、教材の少ない言語を選びがちだ。加えて、これまでに気になっていた言語のいくつかはすでに少し齧っている。そのため、候補としてはビルマ語やチベット語あたりが真っ先に浮かんだ。本来なら、こういう授業は新しい内容がほとんどなくて退屈になりがちな高校三年の一年間にやってもらいたいところである。学生の視野もずいぶん広がるだろう。ただ、教えられる教員が十分にいるのかという問題も出てくるが。
9月に入ってから滞っていたデンマーク語の学習を再開した。相変わらず発音には慣れず、文字の読み方にもまだ自信が持てないため、分からないときは、正しいかどうかはよく分からないがGoogle翻訳で確認している。なお、デンーデン辞書ならかなり詳細なものがネット上にあり、また発音についてはYouTubeのあるチャンネルが非常に役立つ。