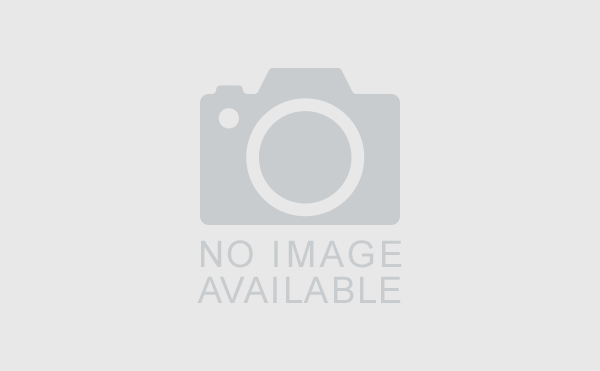外国語独習法
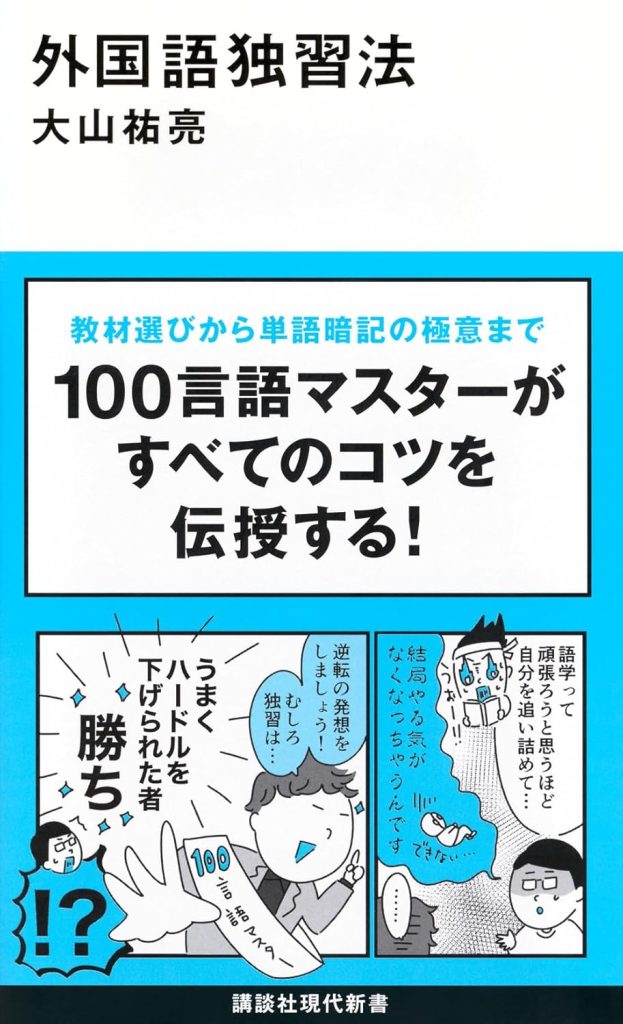
表題書は、いつだったか、刊行直後くらいの時期にタイトルに惹かれて購入したものの、似たような本にがっかりした経験からこれまで手を伸ばせず、かといって処分もできずに書棚の隅に押し込んでいた一冊である。今回ようやく読んでみたのだが、まず何よりも、著者の語学力に圧倒された。まだ三十歳そこそこという若さながら、本職とはいえ十数年で百言語に手を広げ、そのうちいくつかは実用レベルで使いこなしている(と読める)のだから驚くほかない。弟子入りしたくなる。
著者によれば、学習を継続するコツは、さまざまな手段を組み合わせて多角的に、かつ継続できる方式で取り組むことにあるという。ただ、そのいくつかは簡単に真似できるものではない。「手を使う」ことも勧められており、僕も試しに『魔の山』を読んでいたとき、気になった単語や文を筆写してみたが、読む速度がぐっと落ち、集中力も途切れ途切れになって一日で断念した。ただ、ラテン語やギリシャ語のような「文法形言語(本書での分類、語彙の活用や曲用が語彙の繋がりを担う言語)」を腰を据えて学ぶときには、有効な方法だと思う。
アプリの利用については、これまでまったく念頭になかった。というのも、以前ラテン語で試してみた「Duolingo」がどうにも性に合わなかったからだ。そこで今回、もう少し自分に合いそうなものを探してみたところ、「Nemo」というアプリを見つけた。比較的古いタイプで、言語ごとに個別に入手する必要がある、いわゆる単語カード形式のものである。操作はシンプルで音声も付いており、寝床で淡々と続けているうちに、いくつかの言語で無料版(初歩の100語)をあっという間に終えてしまった。無料版の最後に早口言葉が収録されていて、各言語版を見比べてみたかったのも理由の一つである。因みに僕が見た中で字面にギョッとしたのはポーランド語のものだが、モゴモゴと何を言っているのかさっぱり分からないのはデンマーク語のものであった。スロー再生でようやく全体像が掴める感じ。
まだまだ続けたい気分になり、まだ発音も綴りもあやふやなデンマーク語と、放置気味で語彙が一向に定着しないフィンランド語、さらに気まぐれでポーランド語を購入した。昨晩もそれぞれ20語ずつ取り組んでみたが(ランダム順で表示される)、難易度の差が個人的にかなりあり、ある程度慣れていたフィンランド語はすぐに覚えられた一方、ポーランド語は殆どの単語で何度もつまずいてしまい、暫く繰り返すも結局出てこないものも幾つか。後者は次回から10語以下ずつに減らした方がよさそうである。
読みたい本が溜まりつつある。特にミステリー。出張まで取っておくか悩ましい。連載中で10巻未満のある漫画を一気読みしてしまったのだが、それについては別の機会に。