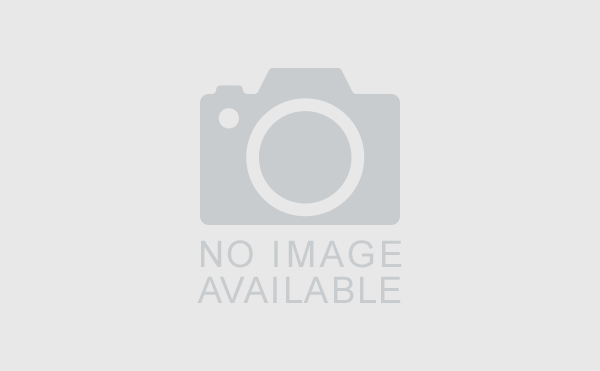イランの地下世界
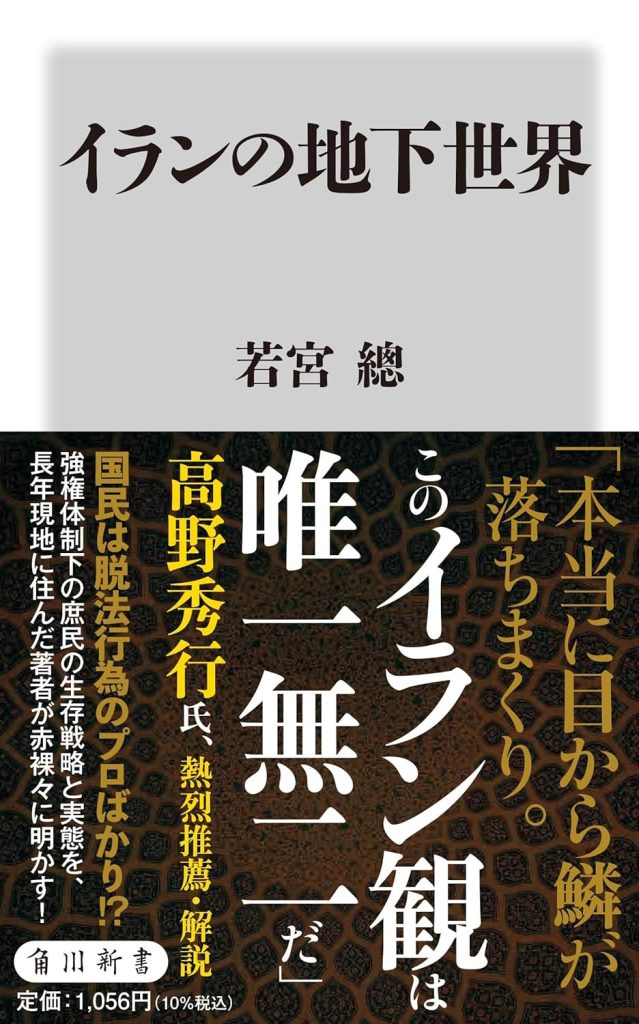
本書は、若い頃からイランで暮らしてきた著者が、その経験を通してイラン社会と人々の実像を描き出したエッセイである。著者自身の体験や交流関係にもとづく肌感覚を頼りに書かれているため、偏りは否めないかもしれない。とはいえ、日本人の多くがほとんど知ることのないこの国の姿を垣間見ることができ、読みやすさも相まって大変興味深く楽しめた。ちなみに著者はペンネームを用いており、内容の性質上、諜報機関にマークされる恐れがあるからだそうな。
イランについては、仕事など特別な縁がない限り、日本人はあまりにも無知である(僕自身がそうなので、多くの人も多分同じだろう)。この無知は、イラン人の自尊心を大きく傷つけることになるらしい。というのも、彼らはさまざまな要因から概して日本に好意的であり、しかも非常に強い自尊心を持っているからだ。この自尊心の高さは、イラン社会におけるさまざまな問題の種ともなっているが、そのあたりの詳細は本書後半に詳しい。
本書の内容に深入りすると僕自身も当局にマークされかねないので、ここではごく大まかに触れるにとどめたい。現在のイランでは、イスラム体制への反発と「イスラム教疲れ」が広がりつつあるという。著者は、今後10年ほどの間に起こりうる政治的変化として、次の三つのシナリオを挙げている。第一にイスラム体制の崩壊、第二にイスラム体制を維持したままの民主化、そして第三にイスラム体制のさらなる強化である。10年という目安を設けているのは、現体制の最高指導者が高齢であり、近い将来に権力交代が避けられないと見られるためである。
前半を読んだ段階では、第一か第二のシナリオしかあり得ないだろうと感じていた。ところが第5章「イラン人の頭の中」を読み進めるにつれ、むしろ第三のシナリオこそ最も現実味があるのではないかと思うようになった。それほどまでに、イラン人の国民性は徹底した個人主義であり、隣人の成功を強く妬み、社会的な関係の中ではどうしても「独裁者」的な振る舞いが顔を出してしまうのだという。
本書があまりに面白かったので、ついネットで見つけたペルシャ語文法の古本を安価で購入してしまった。気になった国や文化が出てきたら、とりあえず言語から触れてみるのが習慣になっている。ただ、今はそこまで手を広げる余裕がないため、届いてすぐに段ボール箱(手元に取っておきたい本や今すぐ読まない本の保管庫である)にしまい込む。イランは個人的に今後注目したい国の一つだし、気が向いたらその時にまた。少し前から始めたデンマーク語は、早くも気まぐれにやったりやらなかったりとなっている。