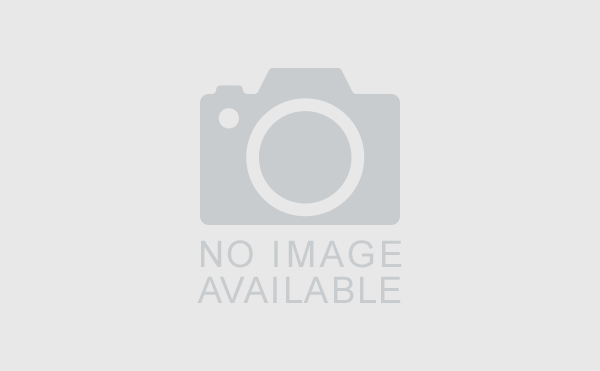人間には12の感覚がある 他
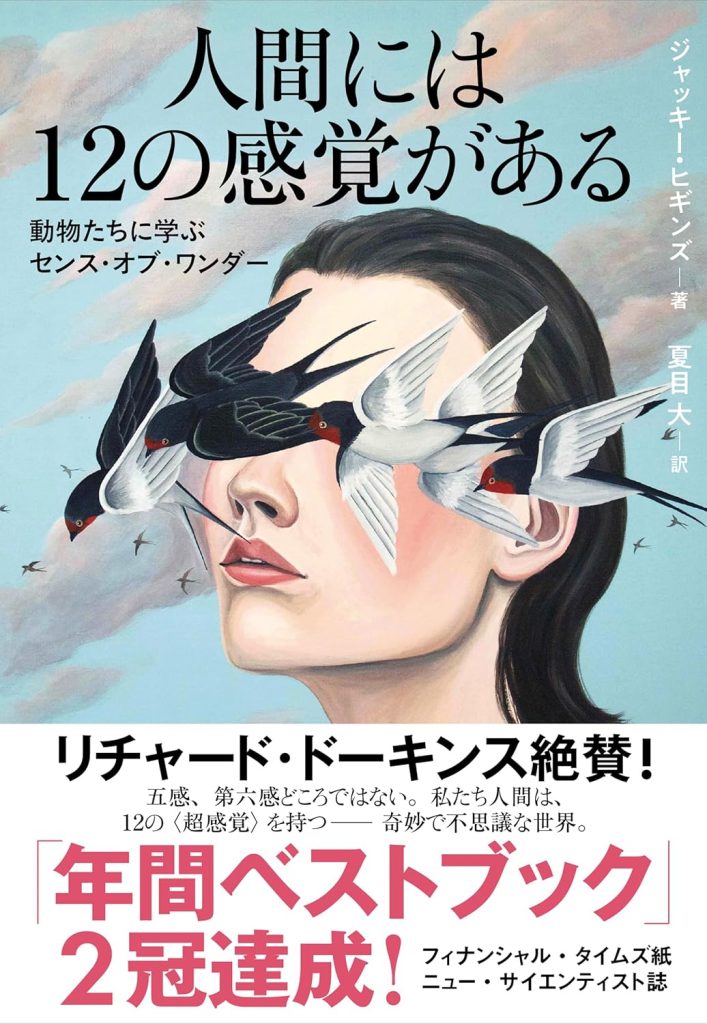
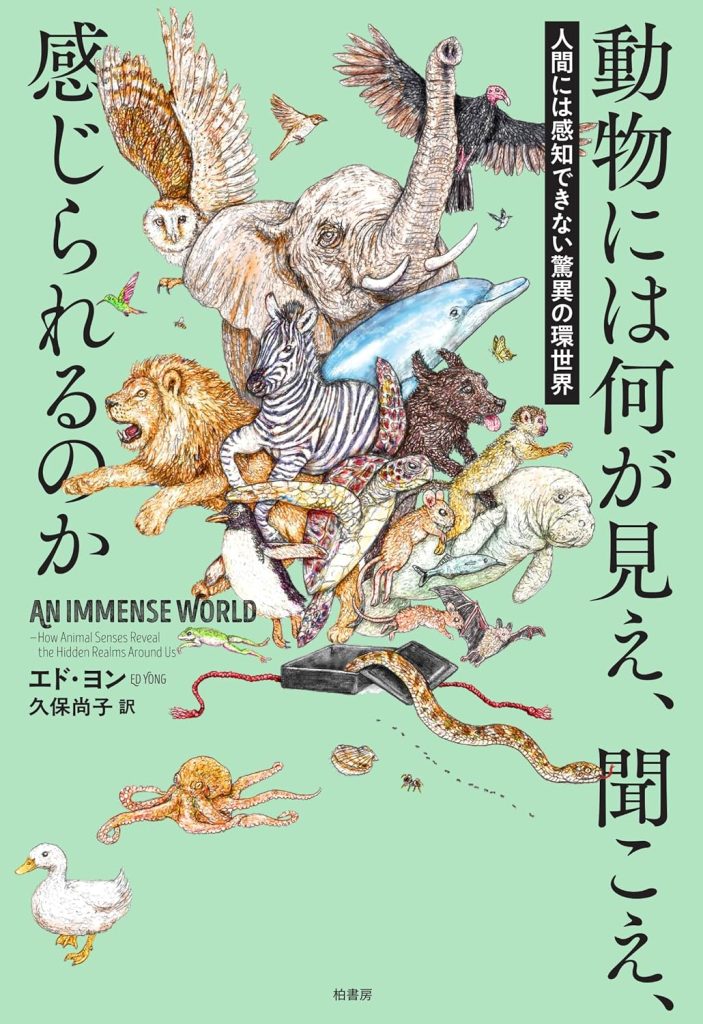
生物学、特に生態学や進化学の本は、もう十年以上もあまり読まないようにしてきた。理由は単純で、ある程度は知っている内容も多く、どうしても文章をじっくり読むというより、情報だけを追ってしまうからだ。読書として楽しめないのである。ただ、新しい発見や最新の研究成果には強く惹かれるので、書店で罠に嵌ってしまうことも多い。
最近の罠になったのが、『人間には12の感覚がある』と『動物には何が見え、聞こえ、感じられるのか』の2冊。誤解のないように断っておくと、どちらもきちんと読めば非常に面白い(いや、「面白いはず」である、なにせ読み通してはいないので)。最近の生物学のトピックを蘊蓄として楽しみたい人には、かなりおすすめできる。ただし難点を挙げるとすれば、知識の寄せ集めという印象が強く、内容がやや断片的で浅い。そこから更に沈考したくなるような深みには欠けるかもしれない。
まずは『動物には何が見え、聞こえ、感じられるのか』。これは5月の出張の際に移動中の読み物として購入したもので、車中で半分ほど読んだところで止まってしまっている。一方、『人間には12の感覚がある』は先週から読み始めたが、ちゃんと文章を追ったのは最初の100ページまで。気がつけば、ただ新しい情報を求めてページをパラパラとめくるだけの読み方になっていた。こうなるとせっかくの読書時間が勿体ないので、Audibleで聴くことにした。生物学、とくに進化・生態学に関する本をAudible版で聴くことが多いのも、こうした理由による。文章として読むとつい情報ばかりを追ってしまうが、朗読なら文章を流れとして受け取ることができ、読み飛ばしのようなことが起きないからだ。ただし、何かに気を取られて聴き飛ばしてしまうことは日常茶飯事である。
Audible版の特徴として、先ず両方とも英語が聴き取りやすい。『人間には・・・』の方は僕が苦手とする女性朗読者なのだが、声のトーンが落ち着いていて、抑揚も控えめ。こういうタイプの朗読なら大歓迎である。もうひとつの利点として、内容が比較的断片的なので、不意に聴き逃してしまっても大きな支障がない点である。そういう意味で、この2冊はAudibleと相性が良いと思う。
そういえば此処まで内容には一切触れていなかった。この2冊はいずれも「生物の超感覚」をテーマにしていて、扱っている話題には重なる部分も少なくない。『人間には──』の方は人間の感覚を軸に展開されており、一方の『動物には──』では、モンハナシャコやイヌ、ハナサキモグラといった、超感覚能力をもつ生物種が主役になっている。どちらか一冊と言うなら、『人間には──』の方が僕にはより面白く感じられた。
その『人間には──』から面白い話題を一つ。ある巧妙に設計された実験によれば、人間は光子ひとつ分の光を知覚できるという。もっとも、見えるというよりは、かすかな違和感として感じ取る程度らしい。この実験では、3万回を超える二者択一の試行が行われ、被験者は51.6%の確率で光子の有無を正しく判断したという。ランダムな選択が50%であることを考えると、この差は統計的に有意だとされている。査読を経ていると思われるので一定の信頼性はあるだろうが、何か穴がありそうな気がしてならない。使用された統計量についても、ぜひ明記してほしいところである。
ついでにもう一つ別の話題を。視覚を完全に遮断した状態で神経を研ぎ澄ませば、人間は正面にある障害物の「圧」を感じることができると言う。どういう感覚が関与しているかは伏せておく。