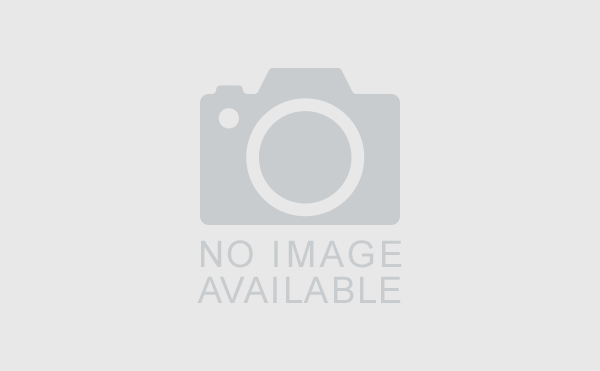誤解を招いたとしたら申し訳ない 他

発言内容を言い直す、修正する、補足する、あるいは撤回するといったフォローアップ的行為は、言語コミュニケーションを円滑に進める上で不可欠である。それは会話において必然的に生じ得る誤解を解消する為の、本来的な行為と言える。考えてみれば、他の人と言語環境?を全く同じくすることは(恐らく)不可能である。ここで言う言語環境?とは、専門的な言葉を知らないのでそれらしい言葉を選んだに過ぎないのだが、単語の意味範囲や言葉選びの癖、方言、思い込みや間違った用法等も含む。文法的な(統語的な?)運用法も含めて、それらは経験を通して習得される。さらに辞書的な定義は巷の用法に基づいた緩い分類枠に過ぎない。である以上、ある言葉の意味が意図した通りに相手に伝わらないという事態は起こり得る。筆者も本書で「なんなら」を「むしろ」あるいは単にリズムを整える程度の意味合いで多用していた。従来的用法しか知らない人(テレビや動画を殆ど見ない人なら有り得るかな?)は引っ掛かるものを感じたに違いない。
例えば僕が、「動物が好きで飼っている」と言ったとする。僕にとって「動物」とは第一義として植物と相対する生物の一群を意味しており、一方で相手が「動物」をより狭い範囲で、例えば哺乳類として先ず思い浮かべる人だとすると、そのうち何処かで会話が噛み合わなくなるかも知れない。相手が何か誤解していると気付いて、「飼っているのはダンゴムシなんだけどね」と補足すれば、会話はまたスムーズに流れるようになる(かな?)。普通は相手の知識背景に応じた言葉選びをするものだけど、それでもこの手のズレは大なり小なり避けられないと思う。
以上は意図した意味のことを言ったつもりの場合であるが、フォローアップが必要になるケースは他に3つある。例えば意図しない意味のことを言うケース。いずれのケースも一般的な会話や発言で十分に起こり得る。会話や発言がリアルタイムで進展する場合、言葉の選択と発言順序に十分な配慮を巡らすことが出来なくなるのが理由の一つ。また即時性を求めるあまり、頭に浮かんだことが意図せずそのまま口を衝いて出ることもある。後々思い返して「ああ〜」としばしば頭を抱える事になる、誰もが経験するであろうあのケースである。
さて、問題があるのは、意図したことを意味する発言を行い、それを撤回する場合。言葉の意味がこのように揺らぐ以上、その意図が発言者にあったかどうかについて本当のところは当人にしか分からないという逃げ道がある。 これがどこまで通用するのか、つまり意図の有無を左右する否認可能性、これは言葉が発せられた情況やその結果として生じる責任の重大性に左右され得る。この点について本書は詳細に解説する。さらにこうした責任逃れは、本来は会話を豊かにする為の機能であるフォローアップ(適切な言葉か分からないけど)的発言の社会的基盤を揺るがす行為である、と警鐘を鳴らす。
もし個人的に、本書の ”Take-home message” を一つ挙げるとすれば、言語を用いたコミュニケーションというものが、いかに複雑な行為であるかという点である。進化について考える際にはDNAだけでは不十分で、遺伝子の相互作用、他個体を含めた環境との相互作用を考慮する必要があるように、言語コミュニケーションは言語だけの問題では無いのである。これから口にする言葉が、置かれた社会の中では何を意味する可能性があるかを考え、それが聞き手にどう受け取られる可能性があるかを推測し、意味を擦り合わせなければならない。その行為の複雑さと、それを誰もが普段当たり前のようにこなしていると言うことに少し眩暈を覚えた。
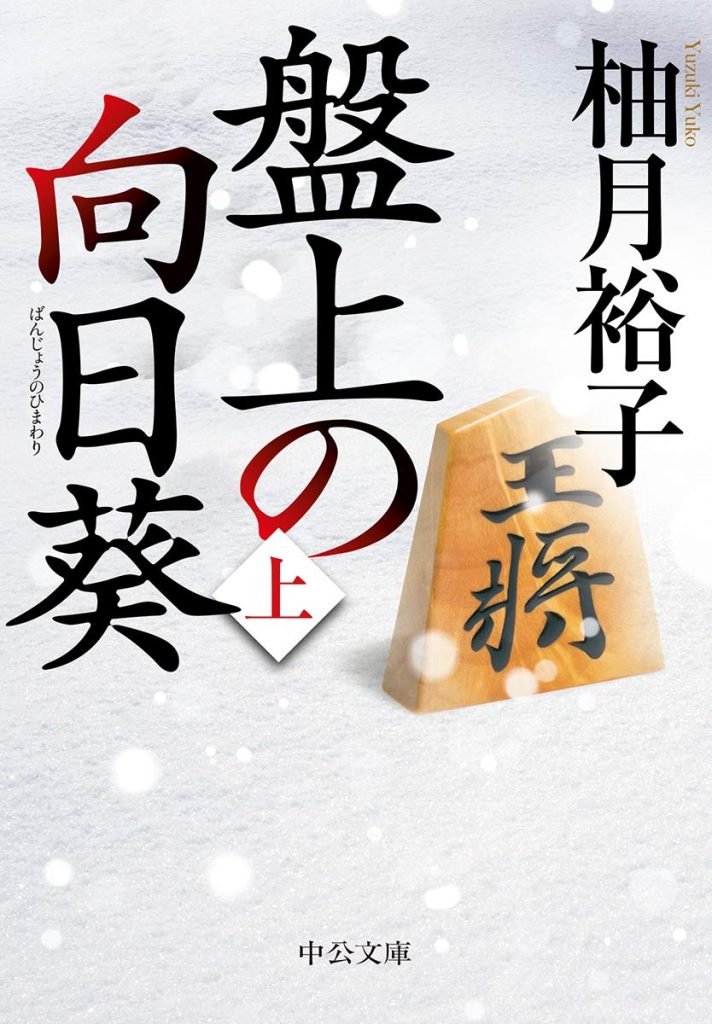
『盤上の向日葵』はましても衝動買い。今年秋に映画公開されるそうで、平積みされているのが目に留まった。賭け将棋師が絡む殺人ミステリーは、詳細はもう忘れてしまったものの何年も前に一度読んだことがあり、本書がその本だったのかどうかは最後まで思い出せず仕舞いである。僕が唯一思い出せる場面風景が本書には無いものなので異なると思うのだが、将棋絡みステリーが幾つもあると思えないのでどうだろう。個人的評価は5点満点の採点で4点。同点の『記憶の対位法』よりやや下くらい。何だか4点ばかりを付けているとも感じるが、どれもそれなりに楽しく、でも再読したい程ではないのだからしょうがない。
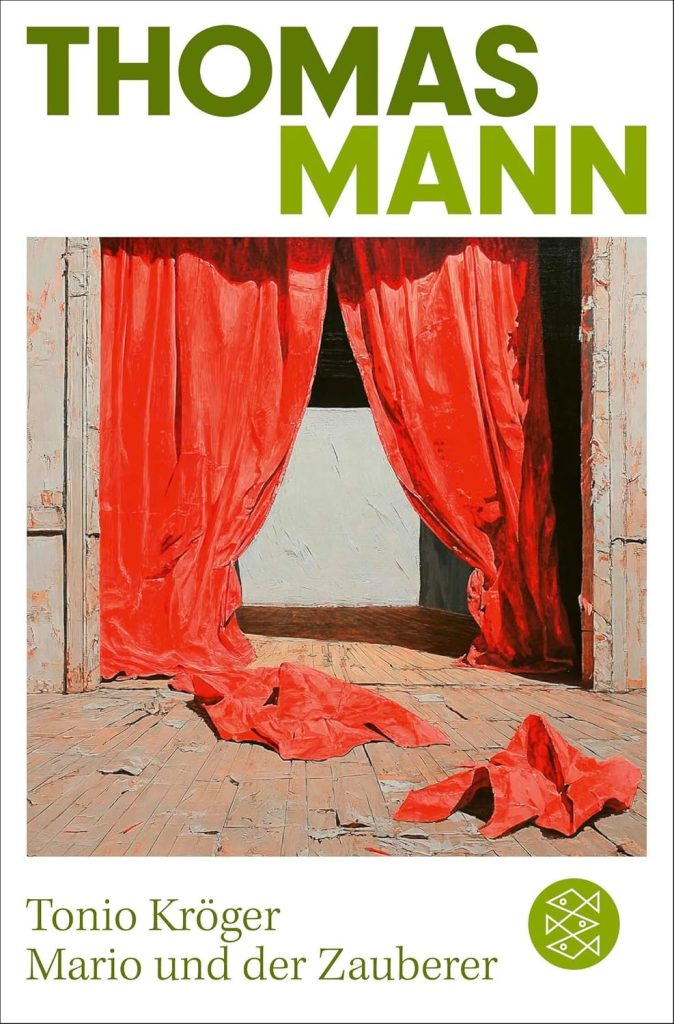
『トニオ・クレーガー』をやっと読了。分からない単語が多くてかなり難儀した。理解が合っているかどうかは不明。目標の本にはまだまだ遠そうである。購入した冊子には別の短編がもう一話入っているが、次は『ヴェニスに死す』を読みたいと思っている。