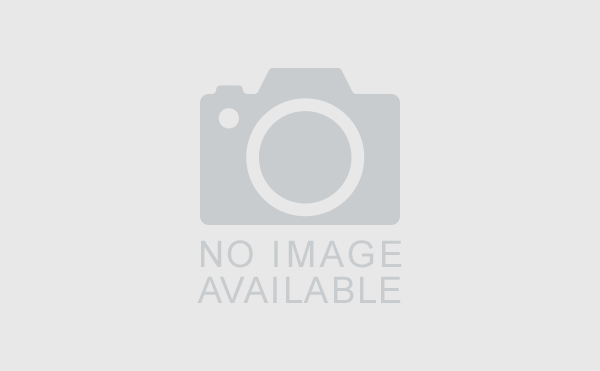ハチは心をもっている 他
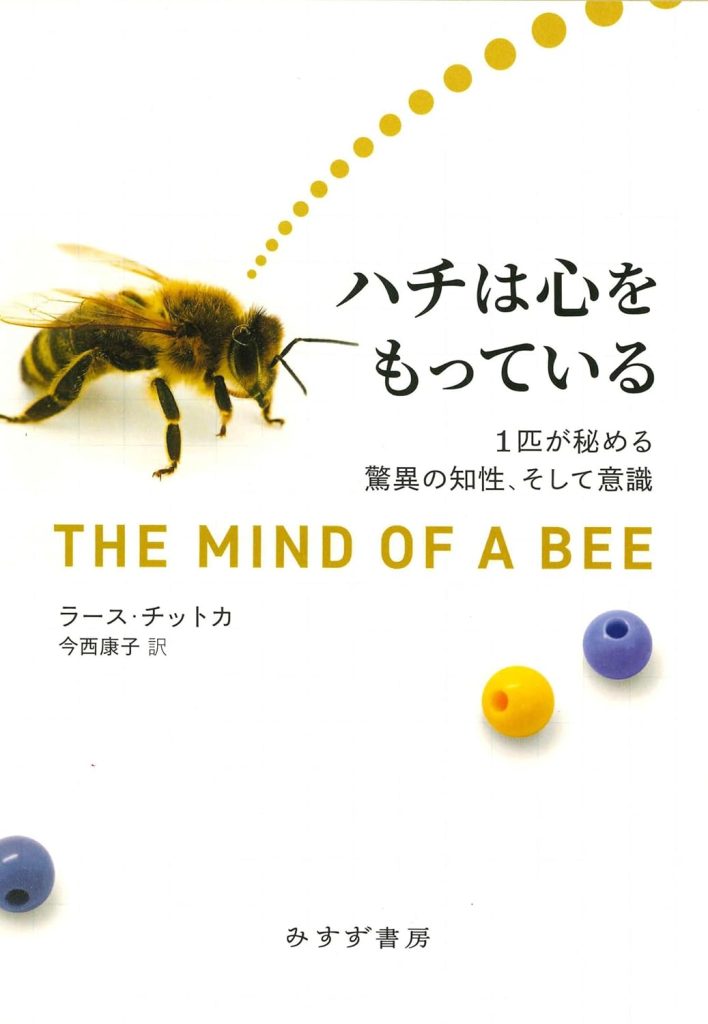
手短に読んだ本の紹介。『ハチは心をもっている』は面白かった。ハチ(そして多分その他の節足動物も)は個別の意識を持ち、どうやら情動的行動も示すらしいということが、主に西洋の昆虫研究者達の長い研究の歴史によって次第に明らかにされてきた。著者自身もこの一連の研究の系列に連なる、現代の第一人者の一人である。巧みな実験によって要素要素が発見されていく、その過程が面白い。その要素の各々は、何も意識を仮定せずとも、機械的行動(あるいは本能的行動?)として説明が付き、ロボットによって容易に実行できる(らしい)。だたしそれらを連関させ、多様な環境に対して適応的な行動を実現するためには、何らかの情報処理中枢を経由する方が遥かに簡単であるという。読み終わって、意識とは何だろうという疑問が残る。
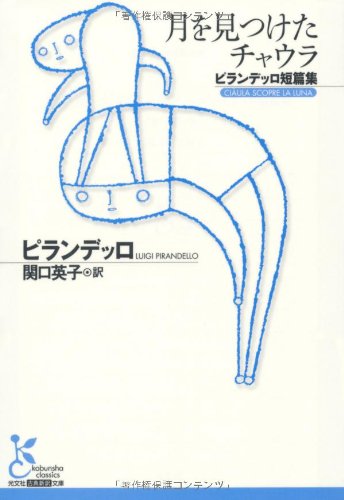
『月を見つけたチャウラ』も面白かった。話が思わぬ方向に進展するかもしれないような短編を集めた短編集である。例えば『使途詩簡朗誦係』。ある寡黙な、信仰を失った副助祭が、道端の石に腰かけていた若い女性に突如声を荒げて「馬鹿野郎」と言い放ち、女性の婚約者に決闘を申し込まれる。或いは『紙の世界』。読書のみに人生を費やしてきた或る読書家の老人が、突然視覚を失い、朗読者を雇う。しかしながらその朗読が彼自身の抱く本の印象と異なるので、結局朗読者には黙読を命じ、彼はその読む様を思い描きつつ本の内容を思い出して悦に浸る。何れも読む速度を落とした方が楽しく読めると思う。
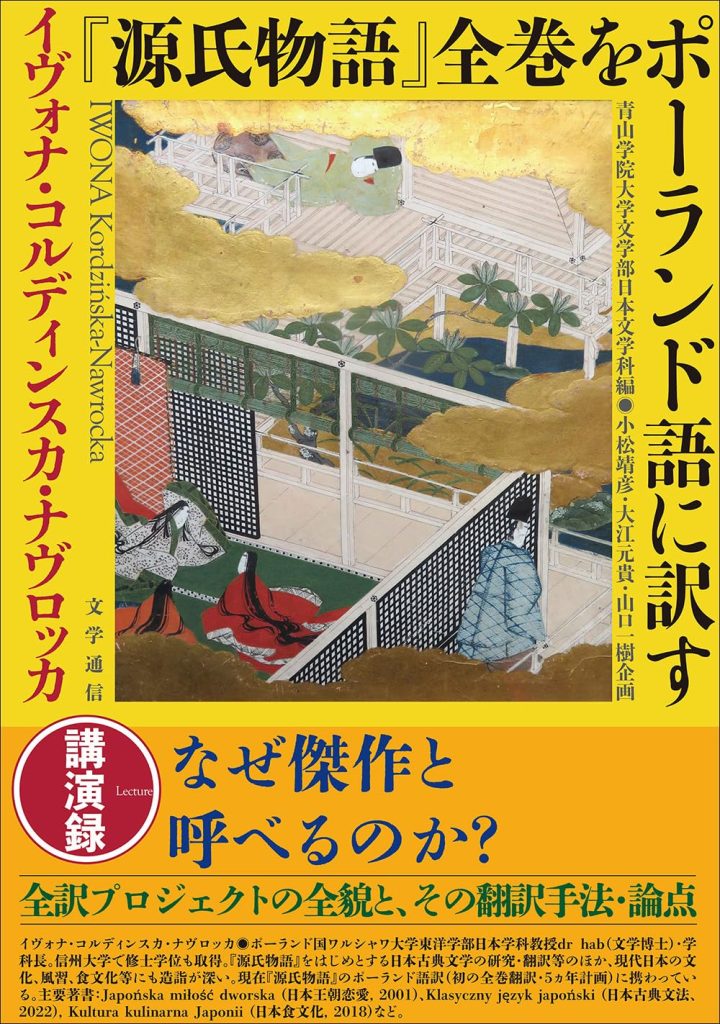
これは数十頁程度の講演録で、小一時間程度で読める内容。書店で現物を確認したら購入しなかったであろう。前半は世界文学としての源氏物語の特徴とその受容について、後半は日本の歌物語をポーランド語版として出版する際の難しさや工夫について語られている。講演者自身が翻訳プロジェクトの翻訳者だそうで、一般読者に分かり易い言葉使いとフォーマットを心がけるそうな。この方針には大いに賛成する。その一方で、注釈や、どうしても別途解説が必要な中世日本固有の文化についての解説が別冊として収録される点はどうだろう。例えば僕が読者なら、別冊を開くのは面倒なので、分からないまま読み進める可能性がかなり高い。