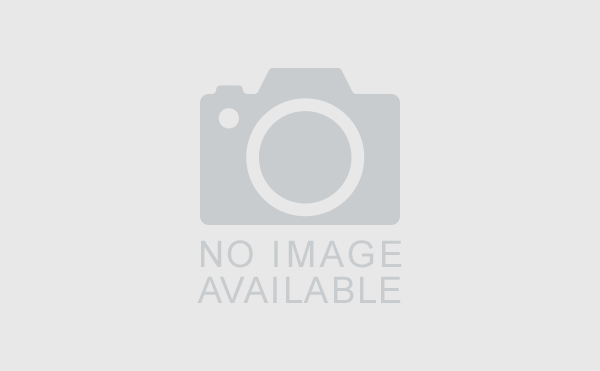オスマン帝国全史 「崇高なる国家」の物語 1299-1922 他
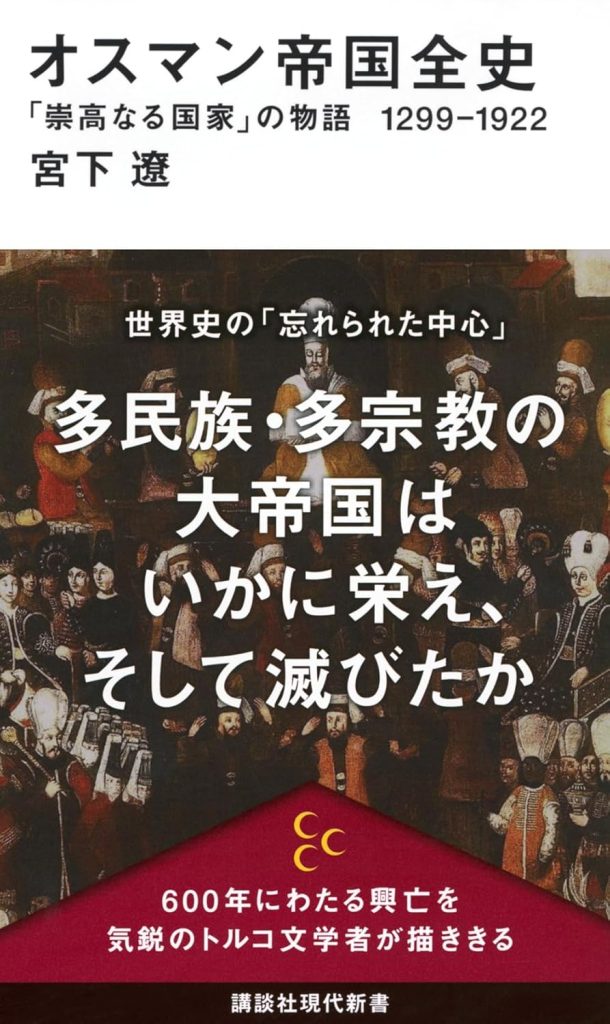
こういう本を読んだという報告。
先ずは『オスマン帝国全史』だが、これは読み応え十分で面白かった。日本史で例えるなら室町時代から明治維新までの武家統治を一気に概観するようなものである。特に最終章、オスマン語(これは誰の母語でもなく、正式文書や上級社会でのみ使用される、帝国の公式語)と、象徴としての「オスマン帝国」という概念についての考察が実に興味深かった。本文は約500ページもあり、今年最もコスパの高い一冊である。難点を一つ挙げるとすれば、トルコ周辺の地理に不案内な人が多いと思われるので、もう少し地図が入っていれば良かった。
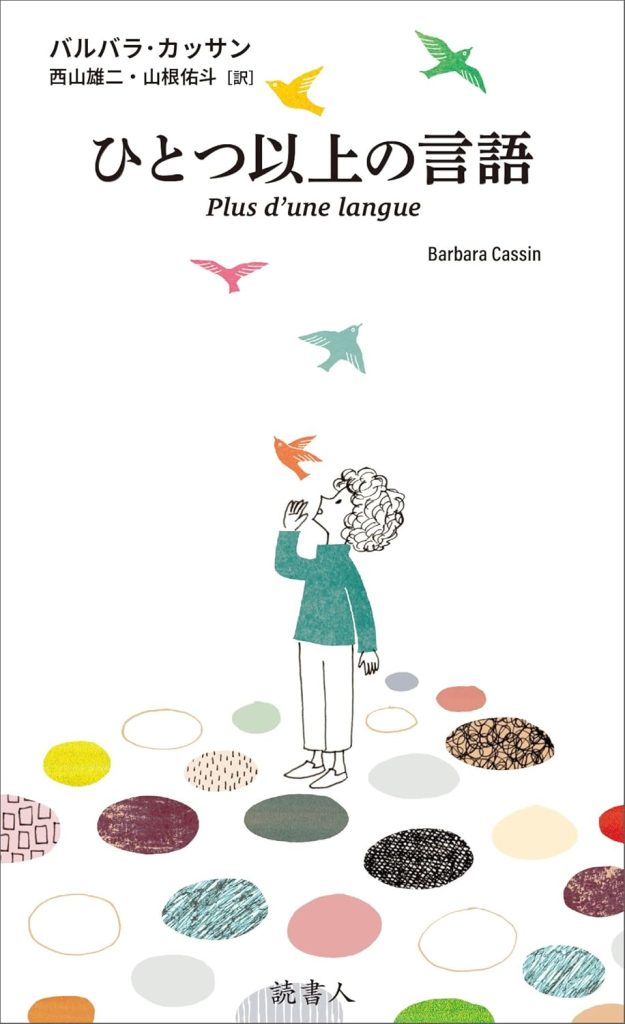
『ひとつ以上の言語』は母語とは異なる言語を学習することの意義について、言語学者が子供向けに分かり易く解説した講演と、その後のQ&Aを書籍化したものである。その主張を簡単に言うなら、「母語しか知らなければ、世界について錯覚を抱えたまま生きることになる(かもしれない)」というもの。つまり、バベルの件で神が人類に罰として与えた言語の分裂は、大いなる福音であった。一時間程度で読める本なので、コスパは『オスマン』の10分の1くらい。でも、面白い。
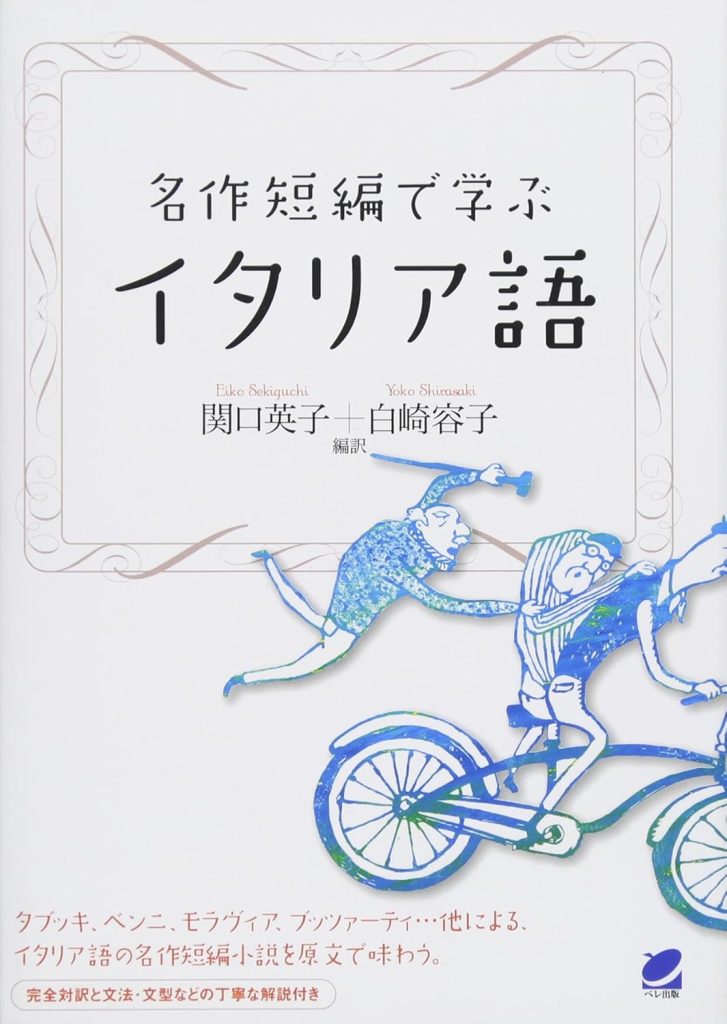
今回挙げた中で一番面白かったのが『名作短編で学ぶイタリア語』。何時購入したのか覚えていないが、不要本を売り払うために整理していて見つけ、イタリア語を最近少し復習したのもあって読み始めてみた。多様な作家の、計10編から構成される対訳の短編集で、文章的に簡単な作品から順に並ぶ。一作品目の『こま娘(Trottolina)』こそ典型的な昔話風で面白さもそこそこだったが、続く『道路を渡るおじいちゃんたち(La traversata dei vecchietti)』から一気に心を掴まれた。特に良かったのが、お話し的にはブッツァーティの『何かが起こった(Qualcosa era successo)』、情緒的にグラツィア・デレッダの『牝鹿(La cerbiatta)』、文章的にはタブッキの『島(Isole)』。10話目は未読。
本書は全てジョナサンにて、毎週末の朝に2時間ほど粘って読んでいた。遠くから「行ってくるニャーン」という声が聞こえ、音楽を鳴らしながら配給ロボットがやって来る様が妙に癖になる。ジョナサンに行く前にはミスタードーナツで、開店の7時から一時間ほど『トニオ・クレーゲル(Tonio Kroeger)』も読んでいるのだけど、こちらは対訳ではなく、分からない単語が多過ぎてなかなか進まない。対訳か否かの差が大きいものの、イタリア語の方がすんなり頭に入りやすい気がする。
巻末には原著の読書案内が付く。気に入った著者から読んでみたいところではあるが、何れも値段が結構張るのが悩ましい。