老子道徳経
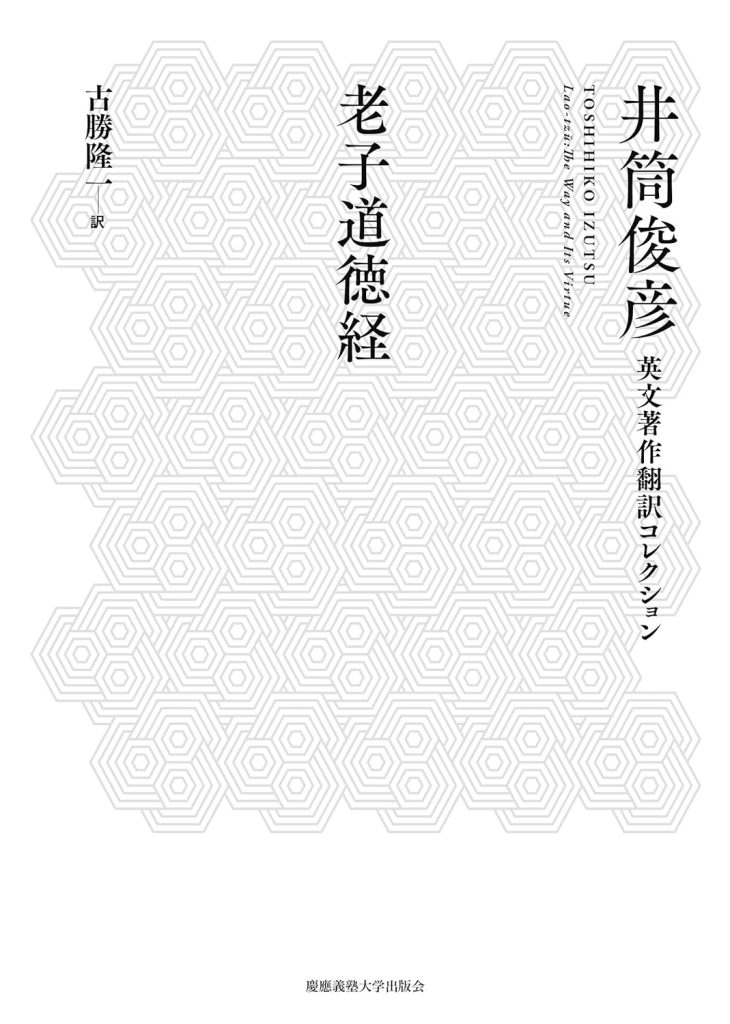
『スーフィズムと老荘思想』には表題書全81章の中から50章が引用されたらしく、それらを含めた全体の内容の確認しようと読んでみた。本書の翻訳は王弼(226-249?)によって確定されたテクストに基づいたと序文にある。翻訳作業に数年先行する1973年に、紀元前2世紀中ごろの漢代に遡る『道徳経』テクストの遺物が湖南省の馬王堆で発見された。このテクストは伝統的に受け継がれた王弼のものとは可なりの違いがあり、当時いまだ記述内容が浮動していたことを示している。他方で王弼版こそが何世紀にもわたって中国文化と歴史的形成に貢献してきた。「極東文化の哲学背景は、『道徳経』のこの特定のかたちで読むことを通してしか、適切に理解することはできない」とする。
この書の著者は老子ということになっているが、歴史上実在した個人かどうかも分かっていない。孔子の逸話に、彼が教えを請いに老子のもとを訪ね、老子を捉え処のない龍であると評したことからも、老子が孔子と同時代に生きた年長者の印象を受ける。一方で『道徳経』を一読すれば明らかなように、本書には孔子以下儒教思想への対抗精神が表明されており、すでに確立されていたであろう儒教を意識した内容となっている。殊に「道」や「名」の捉え方の違いは大きい。その他様々な文献学的考察により、老子がもし実在の人物であるとするなら、紀元前4世紀以降に下げて考えるのが無難であるとされる。
本書が個性的なのは、固有名詞が一切出てこない点にも表れる。「老子が関心を抱いているのは観念であり、あらゆる時空の制限を超えた永遠の観念である。・・・実在する人物や場所ではなく、これらの現象的な形や名の背後あるいは彼方に横たわっている〈何か〉なのである」。しかしながら、注目すべき固有の人格的具体性がこの書物を貫いていると井筒は言う。「一見全く異なる要素すべてが、人格的な統一体としての〈私〉によって、有機的な全体性へと美しく編み上げられている。その〈私〉とは、名無き〈真実〉と完全に一体化した名無き〈自己〉の存在についての具象である。この意味で、『道徳経』ははっきりとある一人の作者の著者なのだ」。一つの人格により語られる一貫した思想が流れていることが強調される。
本書は原著の英語訳の日本語訳ということらしい。幾つか出ている日本語訳書の中で(調べてないのでどれだけあるのか知らないけど)この井筒訳を選んだ理由は、もちろん彼の解釈に興味があったからである。意訳から逐語訳まで幅広いスペクトル幅の翻訳書が出回る中で、後書きに拠ると、彼の翻訳はかなり逐語訳側に寄った翻訳であるらしい。テクストに忠実に読んでいる。だからといって決して読み辛いということはなく、文字下げ(インデント)や行間を駆使して詩的に構成されているのが分かる。とくにインデントが施された箇所は、後書きによると、「通常の言葉を超越した、はるかなる彼方からこの世に聞こえてくる響きととらえられたもの」として井筒が読んだのだろうと本書翻訳者は推測する。さらに重要な点として、老子のようなシンプルで言葉数少ない文章は、文脈を勘案してもなお読み方が確定しない箇所が残る。こうした箇所についても井筒は「別解」として可能的な解釈を載せている。この振幅がまた老子らしいと僕は思う。
因みに、本書は『スーフィズムと老荘思想』を読んだ時のように毎日少しずつ進める読書とは別枠であった。その枠で読んでいる本は、恐らく僕の前提知識が著者とズレるせいだろうか、何を言っているのかよく理解できないでいる。完走できるかも分からないのでタイトルは伏せておく。

『アマテラスの暗号』は文庫新刊書の中に並んでいて、つい手に取ってしまったのだけれど、ひょっとすると以前に読んだかもしれない。記憶が曖昧なのは、それだけ印象が薄かったということ。伊勢神宮の心御柱(だったかな)に祀られる4文字の神名を解き明かすべく、古い神社の家計である主人公たち一行が各地の由緒正しい神社を巡り、日本神話の謎を考察していく。そこにイスラエルと中国政府の思惑が交錯する、といった内容。なお、4文字とは安易なアレでは無く、もう一捻りしてある。それにしても、都合のいい情報を並べて繋いだだけの本書を小説とは呼びたくないなあ。もっと良い形のプレゼンテーションが有っただろうと思うと、惜しい作品である。今回の読書も、すぐに忘れるに違いない。

