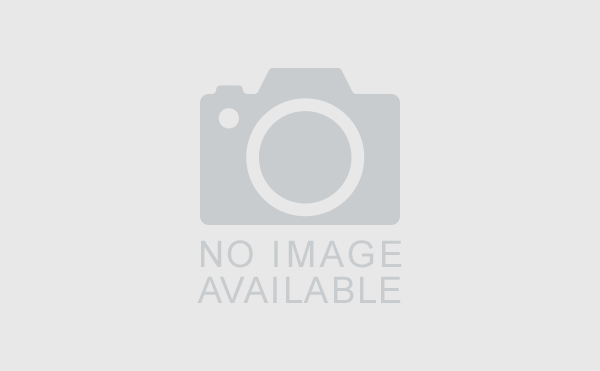記憶の対位法
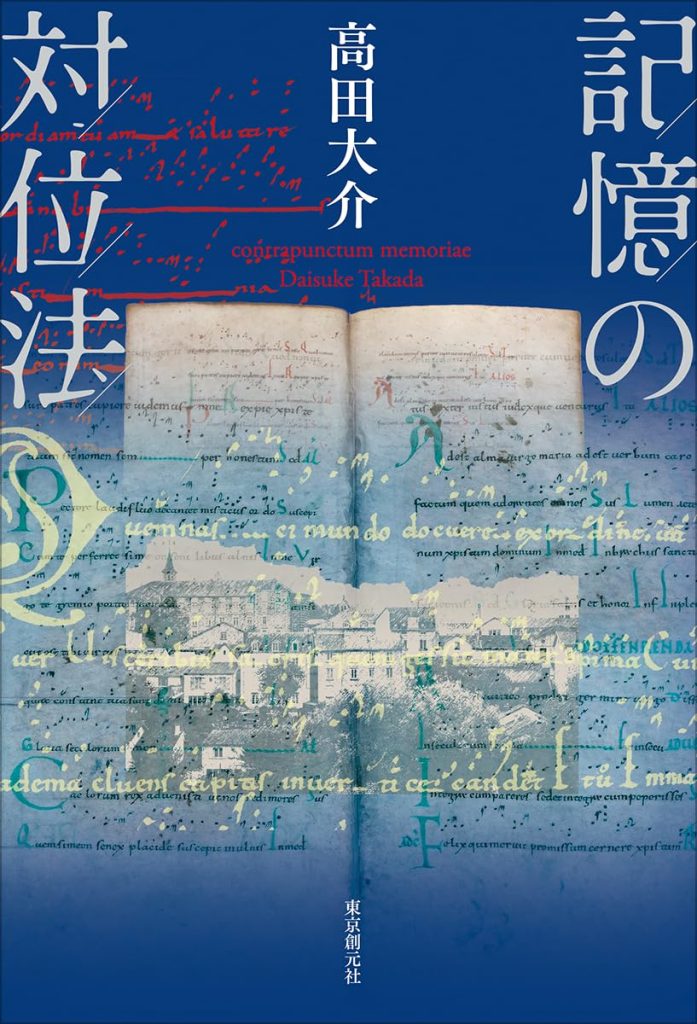
又もミステリーを衝動買い。帯に書かれた「知的探求の喜び」という売り文句に惹かれた。その読後感は十二分に満足のいくものだった。ただし、「ミステリー」とは言うものの、『ダヴィンチ・コード』の様にアクロバティックな展開と蘊蓄の連鎖を期待すると肩透かしを食らう。同様に娯楽要素がそれほど高いわけでもない(個人的に)。じゃあ何が面白かったかと言うと;
この物語は主人公が祖父の遺品を整理するうちに発見した、数片の紙切れに書かれたラテン語らしき文字の解明から始まる。フランスが舞台である。祖父は第二次世界大戦時にナチへの協力者(コラボ)としての疑いを受け、世間から隔たった山村に隠れ住んでいた。これが主題の一つ目。主題の二つ目は現代フランスにおける移民を巡る社会問題であり、これには主人公の出自が大きく拘わる。三つめの主題は遺産から見つかった紙片が表しているものに関与する。これら三つの主題を繋げるのが(音楽の)対位法である。
この繋がり、僕は最終盤も最終盤まで分からなかったが、言われてみれば成程と、久々にあの妙な晴れやかさ(良い物語を読み終わった時のスッキリした満足感のこと)を得た。ただし道中は少し辛抱がいる。例えば新聞記者である主人公と彼の上司が移民問題やテロについて長々と議論を交わす個所など、それが物語全体にどう関わるのか正直全く見通せなかった。個人的採点は5点満点中の4点。例えば先日の『spring』は、道中は確かに爽やかで楽しかったが、半ばを過ぎると胸やけがした。それよりも好みである。

表題書の後続として、今現在是非とも読みたいものが無くなったので、だいぶ前から宿題として取ってあった『イタリア語の起源』を読むことにした。一般的な教科書サイズなので寝ながら読むには手が少ししんどいが、それにも増して面白い。イタリア語(とラテン語も?)のある程度の知識は必要である。そうでなければ読む動機もまた無いだろうし。読み始めたばかりなので、詳細は読み終わる頃にまた。