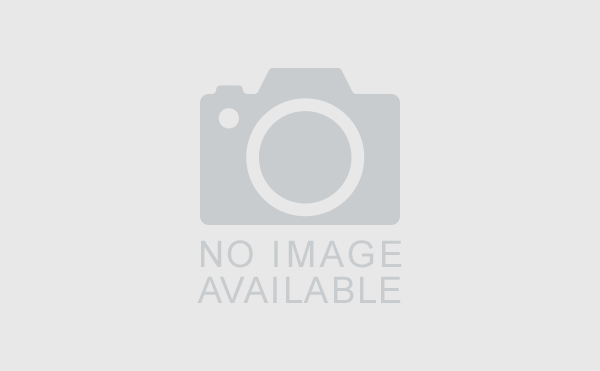呪文の言語学: ルーマニアの魔女に耳をすませて
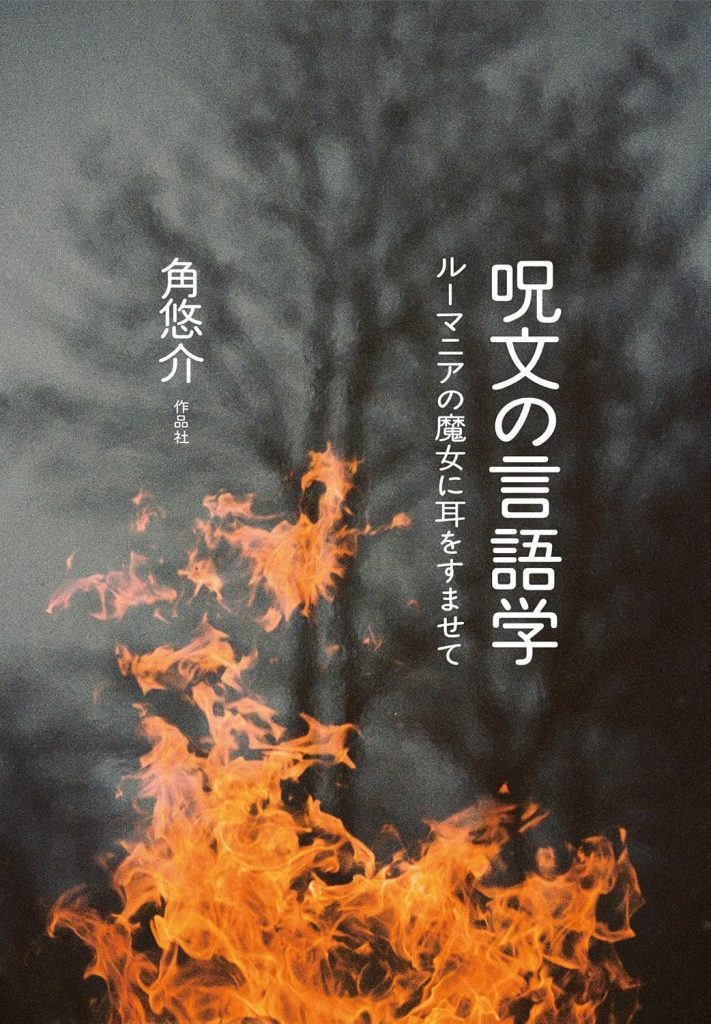
『ロマニ・コード』の著者の新刊書である。著者の経歴については、そちらと併せて本書の冒頭にも簡単に紹介してあり、これが一般的な日本人の歩む経歴とは随分と異なっていてかなり面白い。羨ましいさを覚える程である。そんな彼が高校卒業後にルーマニアへ留学する準備としてルーマニア語の先生となったのが、とある武蔵野市在住のルーマニア人女性であり、この人も実は魔女の一人であった。
ルーマニアは民俗学研究の中心地とされ、他国において失われた諸種の伝統文化が現在もなお定着している地域であるそうな。中世における魔女狩りの影響と、近代の啓蒙主義および科学信仰への過度な傾倒を経て、西ヨーロッパでは土着信仰を反映した魔女文化は公の場から姿を消した。一方、東欧諸国における魔女狩りの影響は比較的軽微であり、特にルーマニアにおいては、複数の要因により、かつて欧州各地に伝播していたであろう古来の魔術が自然な形で維持されている。これらの魔術は主として日常生活に密着した性質を有し、農村社会においてひっそりと保持され、口承による実践を通じて、主として女性によって継承されてきた。
ここでいう「魔術」とは、ファンタジーゲームにおけるメイジの「ファイヤーボール」や「ポリモルフ」のような、背徳性や興行性を伴う超常的な力の行使を指すものではない。むしろ、日常生活に根差した行為、すなわち「痛いの痛いの飛んでけ」といったおまじないや願掛け、古来の仕来り、祈祷等に分類されるものであり、生活上の知恵や心理的効果に基づく行為として理解される。これらの行為を様式化したものが魔術であり、その言語的要素が呪文である。初詣、厄払い、御守りなどの儀礼様式が現代においても尊重され、「ことだま」という概念も現代に残る(どれだけ真面目に信じているかは知らないが)日本で育った人にはそれほど抵抗感なく受け止められる文化ではなかろうか。
さて、呪文にはいくつかの決まりごとや要素が存在することが示されており、それらを分析的に説明したのが後半部分である。読んでいて必ずしも娯楽的とはいえないが、概念的な興味においては非常に示唆に富む内容である。本書の白眉の一つは、その後に紹介される、著者自身が考案した「さいきょうのじゅもん」である。ここに著者は呪文の全ての要素を盛り込み、進行する薄毛に対するカウンタースペルとして惜しげも無く提示する。もう一つの白眉は、本書巻末に収められた、著者のルーマニア語の先生でありかつ友人でもある武蔵野魔女との対談である。彼女の生活や思考に自然に魔術が溶け込んでおり、現代的な常識との落差に驚かされる。
表題書のほかに、Kindle Unlimitedで読んだ本もいくつかあるが、いずれも大して面白くなかったので、それらについてはネタに困ったときにまた触れることにする。